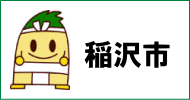議会報告SERVICE&PRODUCTS
会議録・映像

令和7年9月定例会 9月11日) 映像はこちら
1.結婚活動支援について
(1)これまでの結婚活動支援事業について
(2)愛知県のあいマリについて
(3)今後の取り組みについて
2.GIGAスクール構想について
(1)今まで運用してきての良い点悪い点について
(2)今後の取り組みについて
議事録は後日UP
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和7年3月定例会 3月10日 映像はこちら
1.シティプロモーションについて
(1)シティプロモーション事業の取り組み状況について
(2)PR大使の活用について
(3)今後の取り組みについて
2.中途採用について
(1)社会人採用試験について
(2)SPI導入について
(3)今後の展開について
以下は議事録
◆9番(杉山太希君) (登壇)
皆様、おはようございます。
昨年は一般質問で議会を止めてしまい、大変申し訳ありませんでした。
1番で大変緊張、そしてちょっとトラウマもありますが、シティプロモーションについて、そして中途採用について質問席のほうから質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(降 壇)
それでは、始めさせていただきます。
全国的に人口減少社会に突入し、本市においても2005年にピーク、人口は減少をしております。このままいけば、2040年には1万人以上の減少が予想されております。そのため、本市においても、将来にわたって人口減少に歯止めをかけるための対応が必要となっており、都市計画や住宅政策といった各種まちづくりの進捗と足並みを合わせながら、本市で暮らすことが魅力的だと思っていただけるよい都市イメージをつくり上げ、シティプロモーションを推進することが肝腎だと思っております。
昨年度、総合政策部シティプロモーション課を設置した経緯についてお聞かせください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
議員のおっしゃるとおり、人口減少に対する施策を展開する中で、移住・定住の促進に向けて知名度やイメージの向上を図り、本市の魅力を効果的に伝えるため、シティプロモーションの推進は重要です。そこで令和5年4月に、大規模な組織・機構改革の見直しを機に、積極的・戦略的に情報発信をし、市内外への本市PRのさらなる推進をするための部署としてシテ
ィプロモーション課を設置いたしました。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
名古屋駅周辺の再開発などに伴う就労人口の増加を受けて、名古屋駅への鉄道アクセスのよい駅周辺で住宅ニーズが飛躍的に増大しているのですが、本市は名古屋駅への鉄道アクセスがよい駅を有しているにもかかわらず、自然増減は平成24年から毎年減り、社会増減も毎年流出している状況であります。ちなみに、外国人は毎年増え続けております。この人口減少に歯止めをかけ、他都市との競争に勝ち抜いていくためには、まず本市のことを知ってもらい、本市に住みたいと思っていただけるように、本市で住むことの魅力を他の都市以上に高めてアピールしていくことが求められております。
市制65年PR事業では、「ヤバいなざわ」というフレーズを使った動画を作成し、PR事業を展開しておりますが、インパクトのあるもので、若者をターゲットに考えられており、ユーモアのある映像は非常によかったと思っております。
令和5年度の決算によりますと、この名古屋駅でのデジタルサイネージのPR活動に434万5,000円が使われておりますが、このPR事業を実施して、どのような効果が見られたのかお聞かせください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
「ヤバいなざわ」というインパクトのある映像は多くの人の目を引き、サイネージの前で足を止めて映像を見ている方も見受けられました。また、映像放映期間中においてシティプロモーション特設サイトへのアクセス数が上昇したことから、サイネージの映像が本市への関心を高める動きにつながったものと考えております。
さらに、多くの方々がSNSで映像やポスターをシェアしてくださったことで、稲沢市の魅力についてより多くの人の目に触れる機会になったと思われます。市外からの観光客や移住者の増加といった直接的な効果を数値で示すことは困難ですが、本事業を通じて稲沢市の魅力についてPRできたと考えております。
◆9番(杉山太希君)
シティプロモーション特設サイトへのアクセス数が上昇したとのことですが、どのぐらい増えたのでしょうか。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
シティプロモーション特設サイトへのアクセス状況ですが、令和5年度は市制65周年PR事業を展開したこともあり、年間4万9,220件で前年度より約6,000件増加しております。その中でも、名古屋駅でのデジタルサイネージを実施しました令和5年11月中のアクセス数は9,885件と、通常の月の平均値約2,200件に比べ、非常に多くなっております。
◆9番(杉山太希君)
名古屋駅のデジタルサイネージ事業で434万5,000円を使って移住者につながった直接的な効果は数値で示せませんが、1か月に直すと平均2,200件、実施した期間が1か月で9,800件と、5倍近いアクセス、サイトへの増加につながり、稲沢市に興味を持っていただいた方が増えたわけで、それなりのPR効果があったと思います。こうしたPR事業は費用に対して効果を得ることも重要だと思っております。
ここからデータ分析をしていくのもよいかと考えます。例えばアクセス数が増えている、増え出してから移住者が増えたのか、稲沢市の不動産アクセス件数はどうなのか、いつ何どき移住してくるかは分かりませんが、データ分析をすれば、相関性、そしてヒントがあるかもしれません。アクセスが増えれば移住者が増えていく。これだけ実証してしまえば、広告費もこれから予算をつけてもらえると思っております。
また、数年に1度だけですと、企業も年中広告は出しております。今回、広告費は、JR、名鉄のサイトを見ると、どちらも140万円。こう見ると、ちょっと動画の制作費が高いなと思ってしまうんですが、もう一度どこかのタイミングで流すのもありかなと思っております。もう一度データ分析もできますし、よろしくお願いいたします。
令和6年度において広告料の予算が上がっておりましたが、シティプロモーションに関する広告事業はどのようなことを実施されたかお聞かせください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
令和6年度のシティプロモーションの広告事業としましては、プレスリリース配信サービスであるPR TIMESとユーチューブによる広告の2つの事業を展開しております。
◆9番(杉山太希君)
PR TIMESによる広告事業の実施内容と、どのぐらい効果があったのかをお聞かせください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
PR TIMESは、自治体や民間企業からの報道機関向け発表資料を配信サイトにより広く配信するサービスで、そのサイトは多くのメディア関係者や一般の方にも閲覧されることから、効果的なPRが期待できるものでございます。
今年度は2つの情報を発信し、合わせて7万2,600円支出しております。1つ目は、令和6年4月に行ったオリンピア市への中学生派遣事業について発信しました。効果につきましては31社のメディアで取り上げていただき、実施事業者からは、広告換算値が約123万円であったとの報告がございました。2つ目は、ヤバいなざわイラストコンテストの募集記事を発信しました。効果につきましては27社のメディアに取り上げていただき、実施事業者からは、広告換算値が約62万円であったと報告がございました。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
ユーチューブによる広告の実施内容と、どのくらい効果があったのでしょうか。
また、どの地域の方が多く見られているのか教えてください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
ユーチューブによる広告では、令和6年10月21日から11月20日までの1か月間、東海3県のエリアの18歳から44歳までの方を対象に、広告枠でヤバいなざわ動画を流し、19万8,000円支出しております。効果につきましては、1か月間で8万7,940回表示し、4万8,351回視聴され、50%以上の方が最後まで動画を視聴しており、子育て世代にも認知訴求ができたと考えております。
また、視聴地域ですが、視聴回数の多かった順に、名古屋市、岐阜市、豊田市、四日市市、岡崎市となっております。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
ありがとうございます。
私なら広告は全部最初の5秒で飛ばしてしまうので、50%の方が最後まで見ているのはやはりインパクトがあった動画なのかなと感じております。
ユーチューブによる広告によって、サイトへのアクセス数は増えたのでしょうか。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
ユーチューブによる広告を実施した月のシティプロモーション特別サイトへのアクセス数でございますが、令和6年10月は1万565件、11月は1万1,791件と、他の月の平均値約2,600件に比べ、非常に多くなっております。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
今年度行った広告事業は、広告換算のお話もありましたが、費用対効果が非常によい事業を行っていることが分かりました。また、ユーチューブ広告ではターゲットに効果的に発信できることも分かりましたので、この広告事業はぜひとも引き続き実施していただきたい、稲沢市の魅力をどんどん発信していただきたいと思うと同時に、先ほどJR、名鉄の広告費が140万円と140万円、ちょっと高いなと。費用面ではこちらのほうが広告ではよいのかなと思っておりますが、JR、名鉄もインパクトとしてはすごいものがあるので、広告費、これからも増額をお願いいたします。インスタ広告など、ほかにもこういった効率のよい効果的な広告方法があると思いますので、研究、そしてデータ分析、実証していただきたいと思います。
次に、ホームページのお話をさせていただきますが、シティプロモーション特設サイト内の稲沢魅力人では、まちの魅力を伝える方法として人にスポットを当てておりますが、その狙いについてお聞かせください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
シティプロモーション特設サイトの稲沢魅力人につきましては、当市にゆかりのある方にイ
ンタビューすることで、市の職員以外の目線で市の魅力を発信することを目的としています。また、それぞれの業界の著名人にインタビューをしているため、稲沢市にこんな方がいたんだとの声もいただいており、市への愛着を育むきっかけになっていると考えられます。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
こうした今ある魅力的な資源についてブラッシュアップしていく取組は、市民の魅力を再認識してもらう、さらにはそれらの人が周囲に情報を広める効果も期待できるとともに、シビックプライドの醸成にもつながりますので、こうした情報は市外だけではなく、市内の方々にも積極的にPRしていただきたいと思います。稲沢市に移住してもらうのも大事ですが、稲沢市からの流出を防ぐためにもよろしくお願いいたします。愛着は、本当に大事だと思っております。私も10年以上、稲沢市を離れておりましたが、愛着があるとやはり皆さん戻ってくるのかなと感じております。
さて、著名人といえば、インフルエンサーの林 拓磨さんも、稲沢市観光PR大使としてカレーフェスティバルや各種祭りを盛り上げていただいておりますが、シティプロモーション事業に関してどのように活用されておりますか。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
シティプロモーション課におきましても、林 拓磨さんに、今年度から制作しておりますユーチューブ動画への出演や、定期的に行っておりますFMラジオ番組での市のPRコーナーにも出演をお願いをしております。SNSのフォロワー数の多い林 拓磨さんの発信力に期待しつつ、PRに努めております。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
昨年11月に開催いたしましたカレーフェスティバルにおきまして、T.M.Revolution西川貴教さんのキャラクターのタボくんが、新たに稲沢市観光PR大使に任命されました。本市にゆかりのある著名人として清野菜名さんや生見愛瑠さんなど、ほかにも見えますが、新たなPR大使の発掘についてはどのようにお考えでしょうか。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
著名人の発信力は非常に大きく、有名な方ほどその力が大きくなります。シティプロモーションにおきましてもそういった方々のお力をお借りし、できれば大きな効果が期待できますので、周年記念をきっかけとしたPR事業の一手法として考えてまいります。
◆9番(杉山太希君)
次は、ゼロの周年でもあります。JR、名鉄をジャックしたように、70周年はどーんとやっていただきたいと思っております。先ほど答弁にあったように、31社のメディアの取上げで広告換算値が123万円。例えば清野菜名さん、生見愛瑠さんがPR大使となれば、何百社のメデ
ィアが取り上げ、広告換算値も大変なことになると思っております。PR大使になってくれれば、将来絶対に返ってくる投資だと感じております。
また、市長が重い腰を上げて、ねこおじとコラボみたいなものがあれば、この広告効果もすごいんじゃないかなと感じております。こちらもぜひともよろしくお願いいたします。
最後にはなりますが、シティプロモーション全体を通じて、今後の取組についてお聞かせください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
本市のシティプロモーションの最終目標は、移住・定住者を増やし、本市を持続可能な都市としていくことでございます。そのために、まずは本市の魅力や本市を居住地として選択することのメリットなどを効果的に情報提供できるよう工夫してまいります。その上で、各種イベントへの来訪者に本市に魅力を持っていただけるよう、観光施策やスポーツ事業と連携したプロモーションを展開いたします。
令和7年5月に、愛・地球博記念公園において県の主催で実施される愛知万博20周年記念事業「集まれ!あいちの魅力博。」への出展や、名古屋市栄、森の地下街の「まちのたね」へ出展してまいります。また、御当地グルメになった稲沢カレーや特産品などの魅力を発信するとともに、地元スポーツチームとも広く連携し、ここにしかない市の魅力をPRしていきたいと考えております。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
ありがとうございました。
今回は稲沢市のシティプロモーションについて伺ったわけですが、PRにおいては、目的、そして誰に知ってほしいか、そして何を伝えたいのか、そしてどのような方法で受け取ってもらうのかを戦略全体を踏まえて、最適なPR活動を行うことが効果的なシティプロモーションにつながると思っております。
本市は名古屋市から20キロ程度の距離にあり、電車を利用すると名古屋駅から10分程度で到着することができます。そのため、名古屋駅へ通勤・通学にするに当たり、非常に交通利便性が高いまちであるとともに、JR稲沢駅の駅前には大型商業施設なども立地しており、都市的な生活を享受することができるまちであります。
どれだけ稲沢市をPRしても、住む場所がなければ人は来ません。昨今、私の友達が結婚ラッシュであります。3組ほど、止めはしたんですけれども、一宮市に家を買ってしまいました。私の立場的にも大分損害ではあります。家を買いたいときに、よい土地がなければ何ともなりません、そこはタイミングだと思っております。
今年の予算案で、高御堂南地区土地区画整理支援事業、国府宮駅周辺再整備事業が上がっております。調整区域での開発の話も聞いてはおります。早急にお願いいたします。本市には市
街化調整区域が多いという課題がありますが、逆に言えば発展余地の残るまちであり、これからも発展するまちとしての可能性が大きく開けておりますので、本市への転入者及び定住人口が増え、本市が持続的に発展していくことを期待し、シティプロモーションについての質問を終わります。
次に、中途採用についての質問に移りたいと思います。
令和7年4月採用の社会人経験者採用試験を実施した背景は何か。また、応募者の人数、年齢、職種をお聞かせください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
近年、採用試験の応募者数の減少が顕著となり、例えば大学卒の一般事務職では、平成27年4月採用では応募者数が120名のところ、令和6年4月採用では応募者数が37名と低迷していましたので、職員採用試験にてこ入れをするため、社会人経験者採用試験を実施したものでございます。応募者数は追加募集を合わせて177名で、大変多くの方に応募していただいたと考えております。年代別では、30代が最多で86名、49%、次いで40代が72名、41%、20代が13名、7%でございました。職種別では、民間企業在職者の方が115名、65%でございました。幅広い年代の方に受験していただいたことは、試験科目が教養試験ではなく、SPIであったことも要因であると考えております。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
採用の人数が若干名であったにもかかわらず、追加募集を合わせて177名の応募。今回は50歳まで応募ができる思い切った施策ではありますが、やはり小中高生のなりたい職業ランキング上位の公務員。人材不足、応募者数が減っているとはいえ、人気の職業であると思います。ちなみにですが、政治家は100位以下であり、ちょっとショックを受けておりますが。
先ほど答弁にあった今回初めての試みであるSPIでは、試験の特性上、内定辞退が多いと聞いておりますが、実際どうであったかを教えてください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
SPIは、受験しやすいという特徴がある反面、内定辞退者が相当数出るという特徴も併せて持ち合わせています。そのため、当初は内定辞退者が相当数出ることを懸念いたしましたが、今回、SPIを実施した社会人経験者採用試験において内定辞退をした人は一人もいませんでした。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
ありがとうございます。
基本的に近年の新卒採用では、内定辞退率は65%、中途採用ですと10%の数字が出ております。私も令和2年の一般質問で発言をしたとおり、SPI推進派ではありますが、試験科目にSPIを導入した背景はいかがでしょうか。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
SPIは受験者の事前準備の負担を軽くすることを目的として導入しました。具体的には、新卒等の採用枠で実施しています教養試験では、出題範囲が広く、知識を問う出題もあり、事前準備が必要となります。SPIでは、数学系の出題と国語系の出題となっていますので、その点で事前準備の負担軽減につながっていると考えております。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
私は、一般教養試験は受けたことがないのですが、対策に大変時間がかかると聞いております。SPI試験のほうは10年以上前に受けましたので、最近、SPIの本を購入いたしまして解いてみました。やはりブランクがあるせいか、知識がなくても解ける問題もたくさんある反面、対策してないと解けない問題もあるなと感じております。また、SPIは時間との闘いの試験であるとも感じております。どれだけ早く問題を解けるかで点数が変わってくる。この点は思考能力、頭の回転の速さ、やはり人材を採ることにおいてのメリットかなと感じております。また受験者にとって、他社の試験にも使い回せるという負担軽減のメリットもあると思っております。
そこでお伺いいたします。実施した社会人採用経験は多数の応募があり、また応募者の負担も重くなく、SPIにメリットが多いと考えますが、今後の展開を教えてください。
◎総合政策部長(浅野隆夫君)
近年、多くの自治体においてSPIの活用が広がっています。特に報道にもありましたように、愛知県でも令和7年度実施の試験においてSPIが導入される予定で、対象者は大学新卒者も含まれております。費用面におきまして基本料金等を除いた1人当たりの費用は、SPIのほうが教養試験よりも約3.4倍かかります。また、試験日が他の自治体と同一の日程にならないため、受験者が多くなるメリットがありますが、内定辞退者が多く出ることが予想されます。
今後につきましても、他団体の動向を注視するとともに、SPI活用の研究を進め、多くの方に受験していただけるよう、また民間企業経験者等の多様な人材確保にも努めてまいります。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
ありがとうございます。
予算は、多分SPIのほうが上がりますが、新卒採用での利用も御検討していただければと考えております。
今回、土木・建築のほうは応募が少なかったと聞いております。これに関して、近隣の一宮市では、土木系では一次試験が面接から始まり、北名古屋市では全職種で面接が一次試験、二次試験としてSPIを採用しております。職種によってはこういった試みもよいのではないか
なと感じております。
今回の中途採用試験では、専門的な人材を採るという意味合いは少し弱かったのかなと感じております。部署によっては専門的な人材が欲しいということもあるかと思われます。例えば冒頭のシティプロモーション課に一般質問をして思ったんですが、このシティプロモーション課、稲沢市のブランド戦略の考案、広告の打ち出し方、データ分析、そして今苦境のふるさと納税など、これらの施策には、専門知識、広告の知識、会社に対しての営業力などが必要になるのではないかなと思っております。専門的なスキルを持つ人材の確保についていえば、先ほど申し上げた広告関係の場合ですと、やはり民間との待遇面の幅があるから採用が難しいとも聞いております。
専門的スキルを持つ採用試験について調べたところ、ほかの市町村では任期付職員の採用、専門人材を5年で雇用したり、総務省の地域活性化起業人制度、内閣府の地方創生人材支援制度というのがございまして、これを使って専門的な民間企業の社員を一定期間受け入れたりする方法がございます。また、待遇面でなかなか難しいというのであれば、一線を退いた方などを対象にしてみるなど、中途採用試験の幅を広げることで稲沢市に新しい風を取り込み、より生産性の高い組織となることで市の発展につながるよう要望して、一般質問を終わります。ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和6年3月定例会 3月12日 映像はこちら
1.保育士が働きやすい環境整備について
(1)保育士配置の現状について
(2)保育士確保の取り組みについて
(3)保育士の働き方改革について
(4)インクルーシブ保育について
(5)稲沢市の保育の今後について
2.都市計画道路について
(1)尾西稲沢線について
以下は議事録
◆9番(杉山太希君) (登壇)
皆さん、おはようございます。
議長のお許しを、発言の許可をいただきましたので、発言させていただきます。
毎回、この壇上で公明党の加藤議員が経済情勢を話されておりました。今年は日経平均4万円を超えてきましたので、私も自分の見解を話そうと思いましたが、発言時間60分全部使ってしまいそうですので、発言通告どおり進めさせていただきます。
加藤市長は、これまで「子育て・教育は稲沢で!」を掲げ、熱い子育て支援に努めてこられました。子育て支援がどれだけ充実しているか、それがまちの魅力を高める大きな要素であると感じております。
2023年4月、保育士の有効求人倍率は3.3倍となっており、ここ数年は2倍から3倍で推移しております。つまり、保育士1人に対して二、三件の求人があるということになります。
稲沢市でも求人をしばらく調べると、何百件と求人が出てきます。同じ時期の全業種平均は
1.35倍、他業種と比べると保育士の需要は倍になっております。ちなみにですが、中小企業300人以下ですと5.28倍、大企業5,000人以上ですと0.37倍、この5倍を超えてくると人手不足、廃業・倒産が増えてまいります。
今年2024年は、人手不足の廃業が過去最高を記録しております。今後廃業する私立の保育園も出てくるかもしれません。他自治体における不適切保育の報道などを見ますと、保育士の人数が配置基準ぎりぎりであることが一因であったと言われております。昨日市長も答弁されていたとおり、公務員の人気がなくなってきている。今後景気が盛り上がってこれば、歴史的に見ても公務員の志願者は減っていきます。
そして、この有効求人倍率が上がるにつれて優秀な人材が採れなくなる、子育て支援を充実させるとどれだけきれいごとを言っても、まずは保育士をしっかりと確保・配置する、そのための自治体間競争に勝ち抜く、それがなければ保育のニーズに応えられず、「子育て・教育は稲沢で!」が絵に描いた餅になるおそれがあります。
今回は、保育士が働きやすい環境についてをテーマに、市の考えをお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
(降 壇)
まずは、稲沢市全体で保育士は足りているのでしょうか、また民間の保育園等の状況はどうでしょうか、お教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
保育標準時間の1日当たり最大11時間におきまして、国が定める保育士配置基準を満たすとともに、障害などをお持ちで支援が必要なお子さんに対する加配等を行うために必要となってくる保育士数につきましては、何とか配置はできております。ほかの自治体では派遣業者に依頼するケースもあると聞いておりますが、本市ではまだそこまでの状況には至っておりません。ほかの自治体に比べて離職が少ないこともまた要因であると考えております。
また、民間の保育士の配置状況につきましては、公立の保育園同様、何とか必要保育士を配置できている一方で派遣業者に依頼する、あるいは受入れ人数を調整するなど、保育士確保に苦労されている園もある旨聞いております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
稲沢市の保育士採用候補者募集における近年の応募状況はいかがでしょうか。
◎子ども健康部長(高木央君)
保育士の募集につきましては、ここ数年採用予定人数を確保できている状況ではありますが、募集人数に対する申込者数の倍率は、過去3年間で令和3年度採用が4.3倍、令和4年度採用が3.0倍、令和5年度採用が0.9倍と減少しており、令和5年度採用につきましては追加募集を行ったことにより採用予定人数を若干超える応募人数でありましたので、決して余裕のある状
況ではございません。以上です。
◆9番(杉山太希君)
令和5年の0.9倍は少し危機感を覚えます。悪い言葉で言ってしまうと定員割れ、本市を含め、どの自治体も保育士確保には苦労されていると思います。
さらに一口に保育士といっても、正規職員と会計年度任用職員、また会計年度任用職員の中でもフルタイムとパートタイム、パートタイムの中でも様々な曜日、時間帯での勤務体系がある中で、雇用する側と雇用される側の希望をマッチングして保育士をうまく配置していくには苦労があると推察いたします。
これまで本市は必要保育士を何とか配置できたとのことですが、保育士の配置面で何か工夫されてきたことはあるのでしょうか、併せて正規社員と会計年度任用職員の比率もお教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
保育標準時間の1日当たり最大11時間におきまして、特に早朝と延長の時間帯の対応が課題となっておりました。そうした時間帯で働くことを希望される会計年度任用職員の保育士がおらず、短時間の会計年度任用職員の保育士を複数組み合わせることで労務管理が複雑になったり、そもそもそうした短時間保育士を雇用すること自体が難しいといった状況がございました。
現在は、正規職員を早番または遅番という形でフレックス勤務のような形態にするなど、必要保育士数を整理しており、正規職員の比率を高めるなどして対応をしております。
なお、現在担任を持つ保育士における正規職員と会計年度任用職員の比率につきましては、55%、45%となっております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
補佐的な役割であるはずの会計年度任用職員は、正規職員が少ないために同等の保育活動を求められたり、また正規職員も正規職員にしかできない業務があるため正規が少ないことによって負担がかかっている、そういう状況があると思います。今後ともしっかりと必要保育士を配置し、保育のニーズに応えていく必要があると思いますが、将来の保育士確保に向けての見通し、展望についてお考えはどうでしょうか。
◎子ども健康部長(高木央君)
今後、人口減少に伴い生産年齢人口が減少しますと、保育士の絶対数も減少することが予想されます。また、生産年齢人口の減少に伴い、これまで以上に女性の労働力が必要となり、社会復帰も早まることで乳児保育のニーズは高まってまいります。
現在、国が定める保育士の配置基準は、ゼロ歳児には3人に1人を、1歳から2歳児には6人に1人を配置することとしております。乳児保育のニーズの高まりは必要保育士数に直接影響してまいりますし、さらには国は保育士配置基準を改め、4歳から5歳児は現在の30人に1
人から25人に1人へ、また3歳児は現在の20人に1人から15人に1人へと手厚く配置する考えを示しており、また近々1歳児につきましても、現在の6人に1人から5人に1人へと改める予定としております。以上のことから、少子化が進むものの、必要な保育士数は逆に増えることが予想されます。その結果、保育士確保のための自治体間競争が激化することも予想され、今後の保育士の確保につきましては、本市としましても大きな課題と感じております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
保育士の確保が非常に厳しくなる、保育士確保のための自治体間競争が激化するとの見込みを伺いました。
給料が高く、家賃補助なども手厚い都市部に保育士が流出しているという話もお聞きしております。
国が70年ぶりに保育士配置基準を見直したことは歓迎するべきことではありますが、一方で、保育士不足に拍車をかける側面があるとのことで、非常にジレンマを感じております。とはいえ、その条件はどの自治体も同じであります。今後、保育士確保の自治体間競争に打ちかつためには、保育士の確保のために市としてやれるべきことは全てやるとの意気込みが必要と考えます。
そこでお聞きいたします。
保育士の確保について、これまで稲沢市はどのようなことに取り組んできたかお教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
保育士の養成コースがある市内の愛知文教女子短期大学と連携し、保育士の資格を持っていながら保育士の職に就いていないOGらを対象に潜在保育士セミナーを平成28年度から開催し、潜在保育士の掘り起こしに努めてまいりました。また、令和4年度からは参加対象を保育士免許の保持者に限らず、保育士免許を持たない方でも保育現場で働くことに興味がある方も参加可能とし、保育支援者の発掘、さらにはそこからの保育士の免許取得につなげております。
令和元年度からは、保育士等就職支援貸付金制度を開始しております。市内在住の学生で保育士養成施設を卒業後、市内の私立保育園などで保育士として従事しようとする方の就職を支援するため、お一人当たり30万円の貸付けを行うものでございます。なお、市内の私立保育園などに保育士として就職し、引き続き保育士の業務に3年間従事した場合には、その返済を免除しております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
それらの取組のこれまでの実績を教えてください。
◎子ども健康部長(高木央君)
潜在保育士セミナーにつきましては、平成28年度から開催し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年度と3年度は開催できませんでしたが、今年度までに保育士免許を有する方の参加者は延べ58人、復職につながった方は16人でございます。また、保育士免許を持たない方の参加者は延べ27人で、そのうち3人を令和6年度に保育支援者として雇用する予定でございます。なお、これまで保育支援者として働いてみえた方のうち、保育士免許を取得し、現在保育士として働いていらっしゃる方がお二人お見えでございます。
保育士等就職支援貸付金制度につきましては、令和元年度から5年度までに合計38人の方に貸付けを行っております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
愛知文教女子短期大学と連携しての潜在保育セミナーは、保育士養成校が市内にある本市ならではの取組だと思いますし、こうした取組は今後工夫、改良しながら続けていっていただきたいと思いますが、私昨年、35万人都市の高槻市に視察に行ってまいりまして、認定こども園、保育園、小規模園、幼稚園、36法人62園が参加する就職フェアの取組を学びました。答弁の中にあったように、他自治体では派遣業者に依頼するケースもあると聞いております。そして、稲沢市の私立の保育園でも、派遣業者、人材紹介会社に頼んだとのことを耳にしております。
派遣業者、人材紹介会社に頼むと、相場は年収の3割から4割の手数料、つまり1名採用するのに100万円単位で手数料がかかってまいります。令和5年の採用倍率を加味すると、将来稲沢市でも頼むことが出てくるかもしれません。この就職フェアは500万円の事業費で、毎年40名から70名の採用ができているとてもよい取組であります。潜在保育士セミナーですと、年に直すと2名から3名の復職ですので、新しい取組は大変労力がかかりますが、御検討よろしくお願いいたします。
保育士の給料面での待遇も重要だと考えております。令和4年度の保育士の平均月給は約26万7,000円で、全産業の平均より7万円以上低いとの報道もあります。保育士不足の原因は低収入が主な原因だと考えております。
そこでお聞きします。
国は、令和4年2月から保育士や幼稚園教諭等を対象に収入を3%程度、月額9,000円引き上げるための処遇改善を実施するとしておりましたが、本市ではその処遇改善措置を実施したのでしょうか。また、国は令和6年度予算編成過程の中で、保育士等のさらなる処遇改善を検討するとしておりましたが、それはどうなったのか併せてお教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
稲沢市におきましても国の処遇改善措置の趣旨にのっとり、保育士、幼稚園教諭などに対する3%程度、月額9,000円の処遇改善措置を行っておりますが、私立の保育園等においてのみ実施しております。公立保育園につきましては、当初、国から市町村への依頼事項として、公
立施設事業所の賃金引上げに向けた検討とありましたが、その後、国から具体的な手法が示されなかったため本市では実施に至らず、また公立保育園での処遇改善を実施した自治体は県内でも極めて少ないのが現状でございます。
なお、令和6年度のこども家庭庁予算における保育士の処遇改善の内容といたしまして、令和5年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じたものとなっており、公定価格上の人件費も5.2%の改善が図られております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
昨年、平野賀洋子議員の一般質問の中で、現在働いている保育士の処遇改善と将来の保育士人材確保のため、ほかの自治体の動向を注視しつつ、令和5年4月実施を目標に協議してまいりたいと答弁がありましたので、少し残念ではあります。公立保育園の保育士への処遇改善については、人事院勧告準拠の観点から難しい面があることは理解できないでもありませんし、県内自治体でも、公立保育士まで処遇改善措置を実施している例が少ないのはそういうことなんだろうと推察いたします。
ですが、言葉は悪いですが、お金でつるような取組も必要かもしれません。
今、国が保育士宿舎借り上げ事業という補助金制度をやっております。7年間の限定、条件は幾つかありますが、上限を8万2,000円として国が半分、自治体が4分の1、事業者が4分の1の負担であります。稲沢市内であれば、5万円前後の家賃の4分の1と考えれば、1人当たり1万2,500円、私は安いと感じております。
名古屋市は、やっているのですが、近隣市では調べた限りやっていないと感じております。他市から保育士が正職員で来てもらえる可能性、そして稲沢市に住んでもらえる、ひょっとしたらそのまま結婚して稲沢市に永住してもらえるかもしれない。住んでみたら稲沢市はよいまちだと感じてもらえます。今年から婚活事業の予算はなくなる予定と聞いておりますが、よほどこちらのほうが効果を発揮すると感じております。未来の投資としても活用していいのかなと感じております。
とはいっても、やはり保育士になろうという方が稲沢市を働き先として選んでいただいて、離職することなく、やりがいを持って長く楽しく稲沢市で働いていただく、それが一番だと思います。そのためには、保育士の方々が働きやすい環境をいかにつくるかが重要だと思います。日々の業務や残業で保育士が疲弊していないか、休暇は取得できているのか、勤務中に休息が取れているのか、保育士の働き方改革について、これまで稲沢市はどのようなことに取り組んできたかお教えください。あわせて、保育士の平均勤続年数、離職率、平均残業時間の最新値もお教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
これまで保育園現場では、日中は園児を見守り、児童の降園後に保育の計画や教材の準備な
どの業務を行うのが一般的であり、長時間勤務や残業、製作業務の持ち帰りなど負担の重さや厳しい労働環境が指摘され、子育てとの両立が難しいため離職するケースもございました。
保育の質を高めるには、まず働く環境が整ってこそであると考え、保育士の働き方の見直しを行っております。具体的には、ノンコンタクトタイムの導入を図っております。ノンコンタクトタイムとは、休憩とは別に勤務時間中に一時的に保育士が子供から離れ、各種事務仕事などに取り組む時間を確保する取組でございます。残業を削減し、持ち帰り仕事をなくすとともに、心の余裕ができたり、ひいては自らの保育の振り返りや職員間での情報交換にもつながっております。そのためには、休憩やノンコンタクトタイム対応のための短時間保育士の配置が必要になりますし、職員の意識改革、行事の見直し、保育士中心の保育から子供の主体性を中心とする保育への転換など環境の変更も必要になりますが、徐々にそうした環境を整えてきたところでございます。
なお、令和5年度における全保育士の平均勤続年数は12年、離職率は3.4%、時間外勤務の平均は月10時間でございます。以上です。
◆9番(杉山太希君)
保育士が常に子供や保護者と向き合う中で、心と体をすり減らすようでは保育士の質の向上にはつながらないと思っております。なかなか意識しないと、仕事中に気持ちや体をリセットする時間を設けることは難しいと思いますので、十分かつ効率的に保育士を配置していただくとともに、指導保育士や園長らが主導して実効的な取組にしていただくようお願いいたします。
他業種の離職率、時間外勤務、勤続年数の数字だけを見れば、働きやすい環境は整っているのかなと感じました。数字だけでは判断できませんが、このテーマで質問していて、心の中ではすごくホワイトじゃないかと少しびっくりしております。
職員の働き方の見直し以外に保育士が働きやすい職場環境づくりに向けて、これまで稲沢市はどのようなことに取り組んできたかお教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
保育士の負担軽減を図るため、令和元年度から保育支援者の試行的な配置を行っております。保育士免許をお持ちでない方で、清掃業務、遊具の消毒、給食の配膳など、保育に係る周辺業務を行っております。現場の保育士からは保育に集中することができ、また大人の目が増えることによる安心感など、保育士の負担軽減に大いに寄与しているとの意見がございます。
また、保育支援者として子供と関わる中で保育士を目指すようになり、実際に保育士資格を取得されたケースもあるように、保育士確保策としての側面もございます。これまで徐々に配置園数を増やしてまいりましたが、令和6年度からは、インクルーシブ教育の推進に伴い全園に配置する予定としております。
ハード面の取組としましては、タブレット端末を利用した保育業務支援システムを令和4年
度に導入し、令和5年度から本格導入することで、保育業務のICT化を図っております。
具体的な活用としましては、QRコードを利用した登降園管理、欠席連絡、園からのお知らせ、アンケートの配信、行事予定の確認、各種健診結果の確認などでございます。保育士の事務負担の軽減や保護者の利便性につながっているとまた好評であり、今後も利用機能の拡大等に努めてまいります。
また、保育時間中に使用する紙おむつなどを市の費用負担により園でおむつ等を用意し、処分する方式に変更することで保護者の経済的負担と名前書き、使用済みおむつの処分等の手間の軽減が図られ、保育士にとっては、紙おむつを園児ごとに個別管理する業務の軽減が図られております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
保育士の負担軽減のために、市も様々な取組をされていることが分かりました。ほかにも、例えば私立保育園での学校の長期休暇期間中に行われている希望保育、延長保育についてですが、保護者側の意識改革も必要かもしれません。緊急性が低い症状の方が救急車をコンビニ感覚で利用すると、真に救急車が必要な緊急性の高い方が救急車を利用するに当たり支障が生じます。そのため救急医療を持続可能にするためにも、救急車の適正利用に関する周知が必要なように、今後保育を持続可能なものにするには、保護者が休暇等で家にいるときは在宅保育に協力していただくなど、保育の適正利用も周知していかなければならないと感じております。
また、行政ができることとしましては、保護者が毎週持ち帰る布団をサブスク化することで保護者の利便性を高めるとともに、保護者が布団を取りに来るのを保育士が待つ時間をなくし帰宅を早める、一時保育料などのキャッシュレス化を進める、保育士が現金を取り扱う手間をなくすなど、考えられることはまだまだあります。職員の働き方の見直し、人的な支援、ハード面での支援、様々な面で保育士の負担軽減を図っていただき、稲沢市が保育士にとって働きやすいまちであるとの評判が高まり、保育士確保につながることを期待いたします。
先ほど答弁の中に、令和6年度からインクルーシブ保育を推進との話がありました。令和6年度当初予算の中でも大きな事業の一つであり、画期的な取組であると加藤市長もおっしゃっておられました。インクルーシブ保育の推進が現場の保育士にとってどのような意味を持つのか、今までの保育とインクルーシブ保育の違いは何でしょうか、お教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
今までの保育は、特別な配慮を要する子供の個に対して加配が行われる仕組みでしたが、インクルーシブ保育は、個ではなく園という環境に対して加配をする制度でございます。発達障害を持つ子供とそうでない子供は明確に線引きができませんし、グレーゾーンと呼ばれる子、さらに保護者の愛情面でまた問題を抱える子も増えております。本市では現在、子供主体の丁寧な保育を進めておりますが、一人一人の子供の強みを引き出し、社会参加できる大人を増や
していくことが重要であり、そのためにインクルーシブ保育を進めてまいりたいと考えております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
インクルーシブ保育の推進により、保育士の負担が大きくなりはしないでしょうか、お教えください。
◎子ども健康部長(高木央君)
担任保育士が支援が必要な児童も含めたクラス運営を行いますが、支援が必要な子につきましては、担任保育士をフォローする保育士、これをサポート保育士という名称を考えておりますが、必要なときに担任を支える体制を取るため、担任が1人で抱え込むことがなくなり、保育士の負担は逆に減少するものと考えております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
ありがとうございます。
先ほどの答弁、発達障害を持つ子供とそうでない子供は明確に線引きができませんし、グレーゾーンと呼ばれる子もいます。この線引きが一番難しいところかなと思っております。だからこそ難しい補助金でもあると思っております。
近年、政府は単純に保育園が増えるように、保育施設を造りやすい法的な規制緩和を行い、それに伴い従来の法人経営体だけでなく、企業が保育園経営に参入しやすいようにいたしました。
私も保育園について、保育士について調べていると、広告にフランチャイズで保育園を始めませんか、月収100万円以上でといううたい文句で広告が出てきました。数字上でしか判断できませんが、稲沢市内の私立の保育園、決算書、定款とある程度見ましたが、内部留保、経営者の給料が多過ぎるということは今のところないと思っております。この補助金が経営者の財布を膨れ上がらせること、逆に保育士の質を下げてしまうことのないようにお願いいたします。
そこで保育士の質の向上も必要になると思いますが、どのように対応されるのでしょうか。
◎子ども健康部長(高木央君)
本市では、これまでも子育て支援課の子育て相談室なのはなの職員が各園の巡回を実施しており、保育士に対して子供への関わり方のアドバイスを実施しております。今後は保育課としましても、市としてもインクルーシブ保育の考え方を周知したり、研修を実施したり、担当者会議などで情報交換するなどして学びを深めてまいります。
また、保育課の指導保育士が公立、私立全ての園を定期的に訪問し、事業が円滑に進んでいるか、課題は何であるのかなどの把握に努め、対応してまいりたいと考えております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
障害の有無等に関係なく、どのような子供でも伸び伸びと育つことができる環境の中で、様々な関係性の中で生活し、共に育ち合う集団をつくるというインクルーシブ社会の実現を見据えた、その理想は私も共感するものであります。
○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。制度はつくったとしても、来年度以降、これからがその制度に魂を入れていく作業になると思います。事業費も大きなものですので、民間保育園への補助金につきましては適正に支出いただくとともに、定期的な訪問もできる限り増やし、経営者、園長だけでなく現場の保育士の意見も吸い上げながら、お子さんや保護者、保育士にとってよりよいものとなるように、絶え間なく見直しをお願いいたします。
さて、これまでいろいろ聞いてまいりましたが、保育士の確保のためには、稲沢市の保育自体の内容が他の自治体と比較して突き抜けてすばらしいものであれば、保育士が稲沢市の保育の理念に引かれ、稲沢市で働きたい、稲沢市で保育をしたいと思っていただけるのではないでしょうか。それが究極の理想だと感じております。
インクルーシブ保育もその一つだと思いますが、これまでの答弁の中に、保育士中心の保育から子供の主体性を中心とする保育への転換、または子供の主体の丁寧な保育といった言葉がありました。稲沢市のシティプロモーション特設サイトの中でも、子供主体の丁寧な保育が紹介されております。稲沢市の特徴的な保育としてさらに推進していただきたいと思いますし、もっと広くPRしていただきたいと思います。
稲沢市の特色である子供主体の丁寧な保育を推進するなど、保育の中身を充実させることにより、保育士の確保について、またそれに限らず、今後の保育士確保について広くお考えをお聞かせください。
◎子ども健康部長(高木央君)
本市では、これからの時代を生き抜く子供たちに必要な自分で考え自分から行動する力や非認知的能力を伸ばす保育をゼロ歳児から行っております。子供を尊重する保育ガイドラインを設け、市で働く全ての保育士が順守し、丁寧な保育を行う。食事とおむつ替えは同じ保育士が丁寧に関わる育児担当制、特に乳児でございます。子供の主体性、面白そう、やってみたいを尊重し支える保育など、発達に応じた子供の主体性を大切にした生活や遊びの保育環境を整え、子供を一人一人の発達段階を捉えながら、時には見守り、援助が必要であればしっかり向き合っております。
国は、昨年末に少子化対策の具体的な政策メニュー、こども未来戦略を閣議決定し、次元の異なる少子化対策を展開するとしております。本市におきましても、そうした国の姿勢に先んじる意気込みで、保育行政のさらなる充実に努める必要があると考えております。
議員がおっしゃるように、本市の保育の特徴として、今後も子供主体の丁寧な保育を推進するとともに、内外にPRしてまいりたいと考えております。それにより本市の保育に共鳴し、本市での保育を希望する方が増え、本市が保育士をしっかりと確保できるよう努めてまいります。
また、この数年で幾つか公立保育園が休園、廃園となり、それにより必要保育士を賄ってきた側面もございます。出生数の減少や施設の老朽化により保育園の統廃合も進める必要があると考えておりますが、そのメリットを保育士の配置に還元してまいりたいとも考えております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
加藤市長は、「子育て・教育は稲沢で!」をスローガンとして掲げられております。その一層の推進を図るためにも、令和6年度から推進するインクルーシブ保育を含め、本市の特徴である子供を尊重する丁寧な保育、それを他自治体が追随できないブランドの域まで高めていただきたいと思います。それにより、稲沢市が保育士確保の自治体間競争を勝ち抜いていただくことを要望し、次の質問に移ります。
それでは、次の都市計画道路について質問してまいります。
都市計画道路は、都市の骨格を形成し、安全で安心な市民生活と機能的な都市活動を確保するための都市交通における最も基本的な都市施設であります。本市においても、都市計画道路の設備が進められておりますが、現在の設備状況についてお尋ねいたします。
◎まちづくり部長(鈴森泰和君)
本市の都市計画道路は、昭和27年に都市計画決定された路線に始まり、その後新たな路線の追加や幾多の計画変更を経て、現在は37路線、総延長11万7,130メートル、111.13キロメートルとなっております。整備状況につきましては、令和5年4月1日現在で7万2,000メートル、72キロメートル、整備率は61.47%でございます。以上です。
◆9番(杉山太希君)
最初の都市計画決定から70年以上も経過しているにもかかわらず、まだ整備率が61%とは驚いております。残る39%の設備を進めていくとなれば、さらなる年月を要することが容易に想像できますが、市では現在どの路線に整備を注力しているかお教えください。
◎まちづくり部長(鈴森泰和君)
現在、市では東西幹線道路として愛知県と協力し、祖父江町森上地内ほかで進めている都市計画道路祖父江稲沢線、名鉄名古屋本線新清洲駅付近鉄道高架事業の関連事業として、日下部松野町3丁目地内ほかで進めております都市計画道路井之口線、そして西町地内で施工中の稲沢西土地区画整理事業と連携して進めております都市計画道路木全池部線と木全桜木線の計4路線の整備に注力をしております。以上です。
◆9番(杉山太希君)
現在の都市計画道路の整備状況は分かりました。
それでは、次に、私の地元である明治地区を横断する尾西稲沢線についてお伺いいたします。
当該道路は地元で北大通線とも呼ばれ、名鉄国府宮駅やJR稲沢駅へのアクセスに便利なことから多くの市民に利用されております。まず、当該路線の都市計画決定に至る経緯や整備状況についてお伺いいたします。
◎まちづくり部長(鈴森泰和君)
通称北大通線とも呼ばれる都市計画道路尾西稲沢線は、昭和27年9月に北外回り線として都市計画決定されました。昭和38年3月には、日光川から西尾張中央道までの区間が追加され、昭和46年3月に現在の名称である尾西稲沢線となりました。その後、幾多の計画変更を経て、現在は日光川から西尾張中央道までの延長2,700メートルの都市計画道路となっております。
整備状況といたしましては、日光川から国道155号までの800メートル、そして西尾張中央道から西に190メートルの区間が整備を終えており、残る未整備区間は国道155号から石橋6丁目地内までの1,710メートルとなっております。以上でございます。
◆9番(杉山太希君)
本路線は稲沢西春線に接続することから、広域的な交通ネットワークの一体性を高める重要な東西路線であり、本市の課題である東西の主要幹線道路を補完できる機能が十分期待できると考えます。また、木曽川によって二分されている岐阜羽島市と一宮市を新たに結ぶ令和7年開通予定の(仮称)新濃尾大橋へのアクセス道路として、新たな役割も担えると思います。
地元からは、現在道幅が狭く、快適で円満な通行が確保できていないことから、早期の整備を要望する声が毎年出ております。本線の事業化に向け、積極的に取り組んでいただけないでしょうか。
◎まちづくり部長(鈴森泰和君)
本市の東西幹線道路は極めて脆弱であり、特に鉄道交差部における慢性的な渋滞は深刻で、円滑で快適な移動に支障を来しております。このことから、アクションプラン2027や都市計画マスタープランでは、円滑な広域交通ネットワークの形成や東西方向の地域間連携の強化を図るため、都市計画道路祖父江稲沢線、春日井稲沢線及び稲沢西春線の3路線について優先的に整備をしていくこととしております。
先ほど答弁しましたとおり、現在は愛知県と協力し、祖父江稲沢線の整備に全力で取り組んでいる状況でございます。当該路線の全線開通により、市内ほぼ全域にわたる1本の東西軸が形成され、国道155号や西尾張中央道といった南北の主要幹線道路と交差し、市域西側から名古屋方面へ、さらには高速道路へのアクセス道路としての機能が期待されます。しかし、その整備にはまだ10年を超える期間を要し、その後も優先度の高い路線を整備していく必要がある
ことから、現時点では尾西稲沢線の事業化について明確にお答えすることができません。何とぞ御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
◆9番(杉山太希君)
私としても整備の効果を考えれば、祖父江稲沢線の整備に全力で取り組んでいることは十分理解できますし、一刻も早い完成を待ち望んでおります。その一方で、尾西稲沢線の事業化に向けて、先の見通せない状況にあることはとても残念であります。
地元から毎年のように要望書が提出されていることを重く受け止めていただき、早期事業化に向け、これからも御尽力していただきますよう要望して私の質問を終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和5年3月定例会(3月10日) 映像はこちら
主な内容
1.中小企業振興条例について
(1)中小企業に対する認識について
(2)制定に向けた状況について
(3)他市の状況について
(4)条例制定後について
2.企業誘致を図る土地利用施策について
(1)企業誘致にあたっての現状と取り組み状況
(2)清水・生出地区における企業誘致
(3)工業系土地利用の今後について
以下は議事録
◆1番(杉山太希君) (登壇)
皆さん、こんにちは。
議長より発言のお許しをいただきましたので、発言通告に従いまして、一問一答方式にて一般質問をさせていただきます。
昨日の冨田議員のChatGPTが気になりまして、私も調べてみました。今回質問に関わる中小企業について文章を作ってもらいました。長くなるのでここでは読み上げませんが、私より優秀でした。少し気になり、10年後の稲沢市についても文章を作ってもらいました。今後ますます発展していくそうです。いや、本当かなと思い調べてみると、現段階では文章能力がメインであって正確な情報の蓄積には軸を置いていないそうです。それでも私より優秀だと思いますが、質問席にて、中小企業振興条例について、企業誘致を図る土地利用施策について、順次質問をさせていただきます。
(降 壇)
1つ目の項目、中小企業に対する認識について質問していきたいと思います。
稲沢市の中小企業の割合は99.6%であります。中小企業は地域経済を支えているわけであります。今現在、国が実施する産業振興は、私見ですが、中小企業を減らしたいのではないかとさえ感じております。直近の賃上げ税制の税制優遇措置は、法人税、所得税の税額控除に限られます。そもそも納める法人税等が少なければ、利用しても恩恵を受けることができません。人材が賃上げした大企業に流れてしまう。実際報道で就活生の企業を選ぶポイント1位、安定性、2位、社風、3、福利厚生、4、待遇面。大企業、公務員のほうにさらに流れてしまいます。私も一度魅力に負け、大企業に流れた身ですので強くは言えないですが、やはり効率重視
で大企業を対象としたもの、中小企業の中でも大きな中堅企業を主な対象とするものが散見されます。中小企業支援は国・県で十分なのか、市としてはどのように中小企業の支援を考えているのか教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
中小企業への支援につきましては、国・県とともに市も重要な支援主体であると考えております。現在事業者の主な課題である物価高、燃料高対策、環境対応に関し、国や県が取り組む支援は、業界全体への支援、DXやグリーントランスフォーメーション、つまりGXへの対応等、補助額や事業費等が大きくなっています。これらは、小規模な事業者が取り組むにはハードルが高く、市内の中小企業の大多数は、このような大型の支援を受けることは容易ではありません。市といたしましては、より小規模な中小企業を支えることが重要であると考えております。国や県の支援策に関し、それぞれの中小企業に応じ分かりやすく情報を提供すること、商工会議所、商工会と連携、分担し、補助金だけでない継続的できめ細やかな支援を行うことが求められています。以上です。
◆1番(杉山太希君)
私もいろいろ調べましたが、様々な支援があることに気がつきました。ぜひ稲沢市の事業者に情報提供し、優位に進めていただきたいと思います。
全国的に中小企業が減っている現状、稲沢市はそこまで減ってはいないかもしれませんが、今後減っていくことは間違いないと考えます。また、資本の強い他市の企業からM&Aで稲沢市の企業が買われてしまうのも懸念しております。直近ではドンキホーテのユニー買収、ちょっとこれは大きな件ですが、稲沢市の企業が名古屋市の企業に買われている現状もあります。
そこで、創業者、スタートアップでの支援が重要と考えております。稲沢市の創業支援の現状、スタートアップいなざわでの相談状況、他の創業関係者の事業の利用者や実際の創業者はどのぐらいの人数となるか教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
本市においては、創業支援等事業計画に基づき、創業者の支援を行っております。本年度、この計画を大きく改定し、創業経営支援センター「スタートアップいなざわ」を設け、市役所においても相談を受け付けることといたしました。従来から、商工会議所、商工会をワンストップ相談窓口として創業者の相談に対応してまいりましたが、本年度から、稲沢商工会議所により創業スクールを開催いただく等、創業者の支援を拡充してまいりました。
スタートアップいなざわでは、既に創業している事業者も相談の対象としており、およそ半数強が創業前の方です。昨年6月からこの2月まで、9か月間の合計で98名、162件の相談を受け、そのうち55名、92件が創業者からの相談でした。この55名のうち22名の方が2月末までに創業されています。また、稲沢商工会議所の創業スクールには40名の申込みがあり、そのう
ち6名に本市の特定創業支援等事業の認定を行いました。以上です。
◆1番(杉山太希君)
以前の議会で市長が話題に出されましたが、稲沢市からいつかはスティーブ・ジョブズ、マーク・ザッカーバーグが出ることを私も心から期待しております。今回の特定創業支援事業者の中には、ITプラットフォーム企業はなさそうですが、他分野でもよいので、稲沢市を盛り上げPRしてくれる企業、地域の課題を解決してくれる企業が、そして上場するような企業が出てくることも重ねて期待いたします。
さて、創業の支援を含め、中小企業をより支援し、そして守るため、今まで以上に産業振興を行うため、中小企業振興基本条例の制定の検討会議を立ち上げましたが、この条例制定の目的をいま一度教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
中小企業振興基本条例は、地域社会の担い手として重要な役割を果たしている中小企業について地域が一体となって支え、中小企業の振興に係る基本事項を定め、地域経済全体の活性化を図るものでございます。本市においては、愛知中小企業家同友会稲沢支部が中心となり、経済界全体の意見を取りまとめられ、昨年9月に条例制定を進めるよう、条例案を付して御提言いただきました。市といたしましても、これを契機として検討を進めることとしたもので、本年1月に第1回の検討会議を開催いたしました。
今後の検討会議において、条文を詳細に検討いただきますが、条例の制定により、稲沢市においても中小企業の役割、市や中小企業団体、市民等関係者の役割などを明確にし、事業者自らが事業の継続、拡大に向け取り組めるよう、中小企業振興を一歩前に進めていきたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
私も条例制定をすると、個別施策よりも条例のほうが法的拘束力や強制力が強く、稲沢市自身が中小企業ないしは地域産業を振興することを稲沢市役所内部に示すこと、さらには施策の連続性を担保することなど、たとえ市役所の担当者や市長の交代があったとしても連続性を担保してくれる役割もあるかなと感じております。市で行う検討会議の検討はまだこれからですが、提言のあった内容は、既に経済界で十分に議論された内容かと考えます。充実した内容のこの提言書の条例案からどの程度の修正を加えるのか、また他市町の条例文を分析し、例えば他市町の条例で使用される用語が使われる頻度や相関関係を分析して、条例文の最適解を求めるテキストマイニングの手法を活用する等、条例文の作成、修正に当たってどのように検討しているでしょうか。
◎経済環境部長(足立和繁君)
中小企業振興基本条例の検討会議は1月に第1回を開催し、2回目を3月に、3回目を4月に開催する予定です。条文については、今後の会議で検討を進めていただくもので、提言いただいた条例案から、ある程度修正をすることが見込まれます。提言いただいた条例案では、例えば市が実施する施策の基本方針に13の項目を詳細に上げていただいており、他市町村の条例と比較しますと、項目数や文字数がかなり多くなっております。この点については、個別記載の必要性や市としての考え方を提示しながら、より適当な条文となるよう記載の簡素化について御意見をいただくことを考えております。県内他市町の条例、検討会議委員等から提供を受けた先進市の条例を参考にしながら、稲沢市の中小企業の特徴を踏まえた条例文の草案を提示し、まずは検討会議において協議いただくことを考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
私も多くの条例を見る中で、条例の形式も時代とともに変化している傾向が見られます。条例の条項数に関しては、増加の傾向が見られることや項目数のばらつきがなくなってきております。答弁にあった市が実施する施策の基本方針に13の項目を詳細に上げていただいている部分は、他市にあまりない独自性が出ており、1つも削ってはいけないとは言いませんが、どれも重要な項目だと思いますので、できる限り残してほしいなと感じております。
さて、条例を制定し、地域の活性化に役立てている先進市として、福岡県の田川市、大阪府八尾市などがあるが、これらの地域における条例は、どういった点が成功のポイントと考えるでしょうか。また、条例の制定に向けて、意義のある施策を展開するためにも、中小企業の現状や求める施策等について詳細な調査が必要と考えますが、どうでしょうか。
◎経済環境部長(足立和繁君)
中小企業家同友会から、田川市、八尾市について、特に条例を生かした支援が実施されていると紹介を受けております。田川市においては、条例の制定後に市内事業所の全部2,104事業所を対象とした調査を実施されています。条例の検討を行った委員に加え、多くの中小企業、関係者の協力を得て大規模な調査が行われており、その調査で表出した問題に対応を始めています。また、東大阪市に並ぶ中小製造業のまち八尾市では、平成13年に条例を制定され、ものづくりへの支援を中心に幅広い中小企業振興策を展開されています。
いずれの市においても、条例の制定にとどまらず、中小企業や産業の振興を図る会議を設置しており、条例に基づく振興施策が展開されています。本市においても、条例を生かし、施策を推進するための会議を設置することが有効であると考えております。また、令和5年度において、中小企業の現状、施策ニーズを把握するとともに、条例に関係する事項についても調査を予定しております。市内の1,000事業所を抽出し調査してまいりますので、まずはこの調査を実施し、中小企業の実態把握等に努めてまいります。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
八尾市に関しては、制定から約10年が経過したため、条例をより時代に即応したものにするため、全てを改正し、八尾市産業振興会議の中で148項目にわたる施策改善や新たな施策等への提言がなされ、140項目を実現させたとのことであり、この会議の設置が施策に大きく貢献しているとのことであります。また、田川市では、条例の制定時に多くの関係者により協議を行い、制定後には中小企業や中小企業団体、支援機関など、広く協力して詳細な調査を実施されたと聞いております。
ところで、田川市のように数多くの事業所に対し調査を実施するなら、紙の調査で記入するほうも集計するほうも時間と手間をかけるのではなく、ITを活用したほうが入力するだけで簡単なため、回答もより集まると考えますが、次年度に実施する調査はどのように実施されるのか教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
令和5年度において予定する調査は、市内の約5,000事業所から、業種のバランス等を考慮し、会社、個人事業者の合計1,000事業所を抽出し、調査票を郵送する予定でございます。初めての調査実施のため、依頼書、回答票と併せ、返信用の封筒を郵送する予定ですが、依頼書に二次元コードをつけ、アンケートフォームから回答いただけるよう準備してまいります。2回目以降のアンケートの実施や希望される事業者への施策情報の発信に向け、事業所データの収集を図っていく等、できる限りITを活用したいと考えております。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
振興会議での議論や詳細な調査の実施など、条例は制定した後が肝腎となると考えております。振興会議は年何回行うのか、また制定した後、条例によって、稲沢市の中小企業支援がどう変わったのか、制定した条例の検証の仕方はどうするのか。田川市では、産業振興会議と別に、毎月、月によっては複数回の実務担当者会議やテーマごとの研究会を開催し、条例や施策に関し詳細な協議を行っていますが、稲沢市でも産業振興会議とは別に会議等を実施できないか教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
中小企業振興基本条例の制定後は、条例に基づく施策を検討、実施していき、その成果を検証することで条例制定の意義も確認できるものと考えております。条例を基に中小企業や産業の振興を図る会議を設置した場合、この会議を中心として施策の検討、成果の検証を行っていくこととなります。このような会議については、年度ごとの成果の検証、新たな施策の実施に向けた検討を行うため、年2回以上開催することが適当と考えております。また、条例制定の
効果を高めるため、別に会議の場を設け、中小企業や関係団体と協働し、施策の検討、検証を行うことにつながりますので、今後の検討会議の協議によって固めていきたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
会議体の設置に関しては、具体的な中小企業振興施策を検討する場、結果を評価する場を振興会議として設置を明記している割合は、2006年から2017年で59条例、割合は40%、2015年から2019年で102条例、割合は26%。条例数は増加していますが、割合で見れば低下傾向であります。傾向としては、会議体の設置を文言に盛り込まない条例が相対的に増加しております。中小企業振興を行っている自治体で、条例内で会議体設置について明記しなくても施策の検討を行う場があると考えますが、これは市側の怠惰とも考えられます。稲沢市の答弁の中で明記する方向との回答をいただき、安心しております。
条例の制定も急がれますが、多くの中小企業の方と話していると、喫緊の課題として、人材が流出し、市内では働いてもらえない、従業員のいる中小企業はどこも人手不足、また商店や家族経営の工場を中心に、体が動かなくなったら辞める等の声を聞いております。事業承継ほか中小企業には課題が山積しております。これらの課題は待ったなしであり、早期の取組が必要と考えますが、どう考えているでしょうか、教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
今回の条例制定を契機として、会議での協議を踏まえ、中小企業の調査を行い、支援策を比較検討し、実施していく。実施後は、効果を検証するPDCAを回していくこととなります。中小企業における人手不足への支援、迫りくる経営層の高齢化に対する事業承継の支援等、市として対応が求められる課題は山積しております。条例制定を契機として、例えば人材確保の課題に対しては、市民が市内の中小企業に就職された場合に奨学金返済の支援を行う等、早期に検討してまいりたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
条例の制定後にじっくり検討することも必要ですが、奨学金の支援は市内企業の人手不足解消にも、奨学金の返済を背負って働き出した方の支援にもつながり、少しでも早く取り組んでいただきたい支援の一つです。この中小企業基本条例が制定され、すぐに奨学金返済の支援等が出てくれば、つくった意義もありますし、今後制定された後の展開の励みにもなると思います。また、稲沢市に意見や提案ができる場、そして稲沢市と協働で様々な事業がこれからできるためにも、よりよい条例になるようお願いいたします。事業承継においても、例えばスタートアップいなざわで国・県の支援策を案内するだけでなく、創業者と事業承継のマッチングなども行うなど、できる取組から進めていくよう強く要望して、次の質問に移ります。
○議長(出口勝実君)
議事の都合により暫時休憩いたします。
午前11時49分 休憩
午後1時00分 再開
○議長(出口勝実君)
休憩前に引き続き会議を始めます。
杉山太希君。
◆1番(杉山太希君)
企業誘致を図る土地利用施策について質問していきます。
市においては、都市計画をはじめとする様々な土地利用施策に取り組んでおられると思いますが、人口減少対策につながる住宅地供給のための基盤設備に向けた取組だけでなく、私は産業振興、すなわち企業誘致も重要であると考えております。人口減少、超高齢化社会の影響で、今後はさらなる税収の先細りが予想され、行政サービスが低下するとともに、市民への負担増加も余儀なくされるのではないかと懸念しております。
こうしたことからも、直接的な税収アップにつながる企業誘致は、福祉や教育といった市民へのサービスに分配することが可能となり、そうすることでの市外からの移住の選択先となったり、稲沢市民の幸福につながったりするのではないかと思っております。
そこで、ここからは企業誘致を図る産業・工業系の土地利用の促進策についてお尋ねしたいと思います。土地利用施策を語る上で切り離せない都市計画マスタープランについてお聞きします。令和2年度策定の稲沢市都市計画マスタープランでは、土地利用の方向性や今後の取組方針が将来都市構造や地域のまちづくり方針で明らかにされています。中でも、清水・生出地区、赤池・下津地区の各周辺では、工業系の市街地ゾーンとして新たに位置づけされております。そこで、これら2地区が工業系の土地利用を図る地区として位置づけされたのは、どのような経緯があったのかお伺いいたします。
◎建設部長(鈴森泰和君)
稲沢市都市計画マスタープランは、本市の最上位計画であります稲沢市ステージアッププランとの整合を図って策定をしております。ステージアッププランでは、総論として示されたプラン2027において、土地利用方針を掲載しております。その土地利用方針では、広域交通条件に恵まれた本市の特性を生かし、高速道路のインターチェンジ付近や幹線道路沿いを新たな工業ゾーンに位置づけて企業誘致を推進しますと示されております。
この基本方針に基づきまして、国道155号が通り、隣接する一宮市に工業団地が形成されております清水・生出地区と一宮インターチェンジに至近であり、複数の都市計画道路が配置されております赤池・下津地区を工業適地として工業ゾーンに位置づけているものでございます。
これを受けまして、都市計画マスタープランでは、両地区を工業系新市街地ゾーンとし、地域別構想にて具体的な工業地区の区域を図示しております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
それでは、実際都市計画マスタープランに位置づけた結果、民間企業の反応はどうでしょうか。企業からどういった業種の相談があり、件数は増えているのでしょうか、教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
まず立地相談をいただく業種につきまして、両地区ともに広域道路条件に恵まれていることから特に物流倉庫などの流通業が多く、これに加えて、赤池・下津地区では金属製品や食料品などの製造業があります。
次に、相談件数は、立地条件や補助金制度の確認、立地企業が未定である具体性のない不動産業者からの相談なども含め、今年度は2月末現在で62件でございます。これに対し、両地区を位置づける前の令和元年度の相談件数は35件あり、立地相談件数が増加していますので、工業ゾーンに位置づけた効果であると推察されます。
なお、今年度につきましては、清水・生出地区8件、赤池・下津地区14件の相談がございました。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございました。
複数の業種から幾つかの相談を受けているということは、やはり稲沢市は潜在的にも好立地であることがうかがえるのではないでしょうか。市内では、市街化区域の中で企業立地に適した規模や良好な環境の土地はなかなか見当たらないと思います。市街化調整区域であっても、企業からの相談を前向きに捉えてほしいと思っております。また、企業が誘致できた暁には固定資産税等により税収を確保することが期待でき、市の発展も見込めます。人口減少など、現在の社会情勢から将来を見据えると、今から積極的に動くことは重要であると感じております。
そこで、企業を誘致するために市から主体的に活動している取組はあるのでしょうか、教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
企業誘致の活動につきましては、市内企業の市外流出の防止及び市外企業の市内進出を促進させるため、補助金等の優遇制度の案内や立地用地の相談など、一社でも多くの企業の立地を目指し、市内外の企業訪問に取り組んでおります。この企業訪問によって、施設の老朽化を機に市外への移転を検討しているという情報を得て、市内での移転を提案し、市内にとどまっていただいた例もあり、特に日頃から企業との信頼関係を構築していくことが重要と考えております。また、愛知県が東京と大阪で開催する愛知県産業立地セミナーへ参加し、県内での立地に関心のある企業に対し、本市の立地優位性などをPRし、首都圏、関西圏企業の新規立地を
目指した誘致活動にも取り組んでおります。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございました。
市としても積極的に活動していることに期待を寄せるとともに、その活動が実を結び、稲沢市の発展に還元されることも願っております。一つでも多くの企業が市内に立地し、地域の活力となって、市と共に繁栄してほしいと思っております。
稲沢市での企業誘致といえば、近年の好事例は平和工業団地ではないかなと思っております。愛知県企業庁により、1期と2期を合わせて33ヘクタール余りが企業団地として造成されました。既に進出企業が操業を開始しており、旧平和町時代に立地いたした豊田合成も含め、稲沢市で最も大きな工業団地が形成されております。
先ほど私の地元でもあります清水・生出地区では、新たな工業系土地利用を図る地区に位置づけされていることを申しましたが、都市計画マスタープランを見ても、大きな面積の街区で示されております。この地区を平和工業団地のように一体的な工業地として活用できれば、稲沢市に好影響をもたらすのではないかと考えております。
そこで、平和工業団地のような工業地を形成するために、清水・生出地区では企業誘致の手法をどのように考えているのか教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
清水・生出地区については、現行の都市計画マスタープランに位置づけており、地区計画による手法が可能です。加えて、都市計画マスタープランの位置づけにより、都市計画法第34条第12号に基づく、稲沢市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の区域にも該当しますので、この条例により開発することもできます。開発手法については限定せず、事業者からの相談に合わせて企業誘致を推進してまいりたいと考えております。
◆1番(杉山太希君)
幾つかの手法が可能であることが分かりました。しかしながら、都市計画マスタープランが令和2年に策定されてから、依然として工業地としての土地利用が進んでおらず、成果が現れていないと感じております。私も地元であることから、清水・生出地域における土地利用の相談があったことは耳にしておりますので、事業者から一定の需要はあると思っております。先ほど手法については紹介させていただきましたが、その成果が出ていない要因は何でしょうか教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
清水・生出地区については、過去に事業者から開発相談を受けております。当該地区は市街化調整区域ですので、まずは都市計画法に基づく許可が必要となります。これに加えて、農用地区域であれば農振除外と農地転用の許可も必要となり、それぞれの法律に基づく許可要件に
合致することが必要となります。当該地区に限ったことではございませんが、許可等の基準については、区域の取り方、業種や建物の用途など、各種法令により異なることから、それら全てをクリアすることは容易ではありません。そういったことが立地に至らない要因であると考えております。また、これとは別に、社会経済情勢やコロナ禍による影響など、立地を予定する企業側の事情も考えられます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
清水・生出地区は、開発に動き始めてしまった業者もあります。あまり多くは言いませんが、地域の人が混乱しないよう、どうしたらやれるのか、答弁のとおり都市計画法、農地法2つの高い壁がありますが、知恵を振り絞って何とかできるように、そして積極的に動いてほしいと感じております。先ほど経済環境部長からは、企業訪問等、企業へのアプローチも実施していることもお伺いいたしましたので、関係部署が連携して、一件でも多く企業誘致を実現していただくことをお願いいたします。
それでは、今後の工業系の土地利用についてお伺いいたします。
稲沢市は、名神高速道路、東海北陸自動車道、東名阪自動車道、名古屋第二環状自動車道といった広域道路ネットワークの交通環境にも恵まれており、港湾や空港へのアクセスも良好な名古屋圏に位置しております。これらの点からも、稲沢市は製造業や流通業にとって非常に立地的にも優位であると感じております。もっとそのポテンシャルを最大限に生かすべきでもあると思っております。都市計画マスタープランは、令和2年に策定されたところではありますが、工業ゾーンとしての位置づけを増やすお考えはあるのでしょうか、またどういった地域に位置づけていくのか教えてください。
◎建設部長(鈴森泰和君)
本市の企業立地における優位性は十分に認識をいたしております。しかしながら、多くの地域を工業地として位置づけ企業誘致を進めることは、生活や営農環境、排水の問題など、環境悪化を招くことも予想されることから、工業地の集積を図っていくことや工業地としてふさわしい適地を検討することが重要であると考えております。本市におきましては、現行の都市計画マスタープランにおいて、新たに位置づけた清水・生出地区、赤池・下津地区以外にも、平和工業団地や福島工業団地、陸田工業団地など集積した工業地があり、それ以外にも大きな工場が幾つか点在している状況です。そのため、周辺への影響や創業環境を鑑みましても、こうした工業地を中心に工業ゾーンを拡大していくことが望ましいのではないかと思っております。
現行の都市計画マスタープランでは、将来の市内総生産に対応する規模として約30ヘクタールを見込んでおり、これをもって清水・生出地区及び赤池・下津地区において、新たな工業系土地利用を図る地区としております。まずは、両地区を含めて都市計画マスタープランに工業系土地利用として位置づけた区域から、着実に企業の進出を促していく必要があると考えてお
ります。
しかしながら、好機を捉えて企業ニーズに応えていくことは重要でございます。そのことから、場合によっては、状況に合わせた柔軟な対応も考えてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。私も、北海道北広島市、清須市、東浦町と、土地に関していろいろ学ばせていただきました。法の壁は高いと感じますが、思いの部分で解決できることもあると思っております。チャンスが来ることは本当に少ないです。時代の流れ、市長の思い、人々の思いがあればできると感じております。言い訳は幾らでもできると思っています。行動、実行してから、問題が出てきたら後から解決すればいいと思ってもおります。
攻めと守りで、攻め過ぎてバブル期のようにゴーストタウンになってしまうのは浮かれ過ぎだとは思いますが、稲沢市は魅力があります。ポテンシャルも十分にあると思っております。攻めのほうにもう少し重点を置いてよいと思っております。よろしくお願いいたします。
以上で一般質問を終わらせていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和4年9月定例会(9月14日) 映像はこちら
主な内容
1.子育て支援について
(1)一時保育、一時預かりについて
(2)小・中学校の給食費について
(3)保育園等で使用する紙おむつ提供事業について
2.マイナンバーカードについて
(1)マイナンバーカードの現状について
(2)ワクワクいなざわ応援券について
(3)DX人材の中途採用について
以下は議事録
◆1番(杉山太希君) (登壇)
おはようございます。
服部議長より許可をいただきましたので、発言通告に従い、一問一答方式で一般質問させていただきます。
これより質問席から質問させていただきます。
(降 壇)
子育て支援について聞いていきます。
一時保育と一時預かりの違いを教えてください。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難な乳幼児を保育園等で一時的に預かる事業を言い、稲沢市内では現在公立保育園3園、私立保育園3園の計6園で実施しており、一般的には保育園で実施する場合、一時保育と言われております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。利用状況も教えてください。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
利用状況につきましては令和3年度実績で申し上げますと、就労等を理由に1か月14日以内で利用できます非定型的保育は延べ762人、疾病、看護、冠婚葬祭等を理由に1か月10日以内で利用できます緊急保育は延べ299人、育児疲れの解消等を理由に1か月4日以内で利用できますリフレッシュ保育は延べ1,395人となっております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
一時保育を利用しようとしても、予約がいっぱいでなかなか利用ができない現状を聞きます。以前視察で訪れた下関市のふくふくこども館では、1時間500円ほどで随時一時預かりをしてもらえます。
稲沢市でも子育て支援センターなどで一時預かりをすることはできないでしょうか。もし実施するのであれば、どのくらいの予算が必要か教えてください。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
保育園以外での一時預かり事業については、他市でも子育て支援センター等の施設で実施している例がございます。実施に当たっては、開設場所や職員配置等の条件がありますので、現在の子育て支援センター内に専用の部屋がないことから実現は難しいと考えております。
実施に当たり必要な予算としては、初期費用として開設場所の整備に係る費用と、保育士2名程度を常時配置するための人件費が考えられます。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
加藤市長は「子育て・教育は稲沢で!」をスローガンに掲げているが、子育て支援に関する予算は増えているのか、お聞きいたします。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
子育て支援に関する予算に関しましては、「子育て・教育は稲沢で!」を掲げ、子育て、保育、教育、そのほか様々な事業に予算を投入し、毎年新規事業の実施や既存の事業の拡充をし、今年度予算では多胎児育児費用助成事業や保育園ICT化事業などの新規事業を実施しております。
また、子供の医療費については、平成27年度に中学生までの医療費が無料となり、令和2年8月からは高校生の入院医療費、来年4月からは高校生の通院医療費も無料になりますので、予算額は確実に増大しているところでございます。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。数字では出てこなかったですが、私も確実に増えていると感じております。
今回、加藤議員と気が合い、私も明石の5つの無料化に沿ってこの質問をしていこうと思っておりましたが、加藤議員にお任せいたします。
少しだけ違う観点から言わせてください。明石市は、2010年度は126億円だった子供部門の予算を2020年度には257億円に倍増しています。合計特殊出生率が全国平均1.36に対し、明石市の出生率は1.70という驚異的な数字になっております。明石市では、人口が増えたために地域経済が活性化しているのです。明石駅前の図書館、子育て施設や商業施設があるエリアへの新規出店は2倍以上、地価は7年連続で上昇、市内の5年前の中古マンションが2倍の価格となっております。この結果、市への税収もアップしております。明石市の税収は8年前より32億円増え、借金も減り、市の基金残高も51億円増えております。相当な好循環で回っております。
最後に、もう一つだけ言わせてください。明石の立地は稲沢市に似ております。新快速の電車で停車駅であることから所要時間も短く、三ノ宮駅、兵庫の中心15分、空港までは40分、稲沢市も名古屋まで15分、空港まで45分です。立地には引けを取りません。ですが、稲沢市の問題は市街化調整区域でもあります。ここは鈴森建設部長によろしくお願いいたします。
総合文化センターの跡地についてお聞きいたします。
まだ利用方法が決まっていないとのことだが、もし施設を造ることになれば子育て支援として一時預かりができるような機能を持った施設を造ってはどうかと思うが、どうでしょうか。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
総合文化センターの跡地については、どのような施設ができるのか現在未定でございます。保育所等以外での一時預かりについては、保育園で実施している一時保育の現状を見ながら、今後の実現の可能性について考えてまいりたいと思っております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
市長も、先日の6月議会で、地域の皆様から愛されるような拠点として整備を進めてまいりたいと考えておりますとの答弁。そして、六鹿議員からは、若い世代から意見交換をさせていただきますと国府宮駅周辺ににぎわいのある場所をつくっていただきたい。例えばスターバックスとか若者に人気のコーヒー店だそうでございまして、複合施設などを造ってほしいとこんな要望も出ているところでございますと発言がありました。
この国府宮駅から近い場所に一時預かりができる機能を持った施設ができ、スターバックスが入るとなれば、すばらしい複合施設ができる。想像しただけでも市長のおっしゃった地域の皆様から愛されるような拠点になると感じております。ぜひよろしくお願いいたします。
次の質問に移らせていただきます。
小・中学校の給食費を1年間無償化するにはどの程度の費用が必要か、教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
小・中学校の給食費を1年間無償化するために必要な費用といたしましては、小学校で約3億5,000万円、中学校で約2億1,000万円、合わせて約5億6,000万円となります。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。中学校の給食費が2億1,000万円とのことですが、その費用だけでも無償化することはできないでしょうか。
◎教育部長(荻須正偉君)
最近の物価高騰を受け、保護者の経済的負担軽減を図るため、給食費の無償化に取り組む自治体もございますが、本市としましては、子供たちに安心・安全な教育環境を提供するため、老朽化した学校施設の整備を優先したいと考えております。
学校施設につきましては、日々の修繕に加え、来年度以降も学校施設の長寿命化、仮称井之口調理場の建設、大里東小学校や祖父江町学校給食センターの建て替えといった大規模事業、さらにはトイレの洋式化や特別教室への空調設備設置といった保護者や学校現場からの要望への対応などについても検討する必要があり多額の費用がかかりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
難しいですよと、私もそう思っております。ですが、この中学生給食費無料化が実現できれば相当なインパクトになるとも感じております。ちなみにですがお隣、詳しくいえば間に清須
市がありますが、名古屋市は2019年給食の献立の炎上、給食費の値上げによる改善後はある程度よくなりましたが、評判がいいとはあまり聞いておりません。チャンスです。これだけ伝えて、次の質問に移らせていただきます。
これから保育園等で紙おむつ提供事業が始まるが、コストはどのぐらいかかるのか教えてください。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
8月に請負業者が決定し、現在紙おむつ提供事業の利用希望者を調査中ですので、人数としては予算の人数、1月当たり1,100人で計算いたしますと、6か月間で約1,630万円となります。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。保育士の負担はどうでしょうか。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
紙おむつの提供事業につきましては10月からの事業開始のため、まだ保育士に確認はできておりませんが、紙おむつの個別管理がなくなることでコロナ禍で増えた業務負担の軽減が図られるとともに、紙おむつが不足しそうな保護者への催促の声かけが不要となることで心理的負担が軽くなると考えております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。1年で約3,200万円、重ねて答弁を聞きますと保育士の負担も減る。先ほど学校給食で、5億6,000万円に比べればですが、これは6か月以降も継続可能だと私は感じております。ぜひよろしくお願いいたします。
最後に、市長に質問させていただきます。
将来の投資であると私は思っています。子育て支援関連に予算を重点的に配分し、インパクトのある施策を打ち出してほしいと考えますが、市長の考えをお聞かせください。
◎市長(加藤錠司郎君)
先ほどの紙おむつ提供事業もそうですけれども、これは愛知県でも最初に取り組んだ事例だと思っております。
子育て支援に関しましては、様々な施策を打ち出してこれまでも実施してきております。限られた予算の配分について、各方面から慎重に議論する必要ありますけれども、今後も未来ある子供たちの育ちを支援し、稲沢市の発展につなげていくために、子育て関連の事業については、杉山議員の応援もしっかりいただいて、積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。明石市ですと予算の配分ですが、市の職員の給料を減らす、土木費
の大幅な削減をしております。ですが、これは要望いたしません。ですが、予算がこれから増えることはないと感じております。明石市が、投資をすれば後からついてくることを実証してくれました。削れるところ、節税できるところはぜひお願いいたします。
次の質問に移らせていただきます。
本当に気が合うようで、また加藤議員とマイナンバーについても一緒なので、詳しくは加藤議員のほうにやっていただくことにします。
稲沢市、愛知県、全国のマイナンバーカードの交付率について、令和3年4月1日時点と令和4年4月1日時点でお尋ねいたします。
◎市民福祉部長(小野達哉君)
総務省の資料によりますと、令和3年4月1日時点のマイナンバーカードの交付率は、稲沢市が26.6%、愛知県が27.4%、全国が28.3%で、令和4年4月1日時点では、稲沢市が45.0%、愛知県が43.1%、全国が43.3%となっております。令和3年4月では、本市の交付率は県・国の交付率を下回っておりましたが、令和4年4月では、県・国の交付率を上回る状況となっております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。ちなみにですが、1位は宮崎県都城市で驚異の83.9%です。人口も稲沢市より多い16万人であります。
マイナンバーカードの普及促進のために、マイナンバーカードを利用した行政サービスの充実も必要となると思いますが、稲沢市ではどのような行政サービスが利用できるかをお尋ねいたします。
◎市民福祉部長(小野達哉君)
マイナンバーカードを利用した行政サービスといたしましては、全国のコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書などが取得できるコンビニ交付を平成30年1月25日から開始しております。また、令和3年9月1日からはインターネットを利用して住民票の写し、最新年度分の所得課税証明書などの証明書の申請ができるオンライン申請も開始いたしました。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
コンビニ交付の発行件数について、令和2年度と令和3年度を併せて、最新の実績をお聞きいたします。
◎市民福祉部長(小野達哉君)
コンビニ交付の発行件数につきましては、令和2年度は4,025件、令和3年度は9,197件となっており、令和4年度につきましては8月31日現在で4,913件となっており、マイナンバーカ
ードの交付率の上昇に伴い発行件数も確実に増加しております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。普及が進めば職員の負担が減る、そういうことだと感じております。
先ほど話した都城市も、発行する各種証明書について、コンビニ交付のサービスを導入し、市民の利便性向上、そしてコンビニ交付の利用方法が分からないという市民の声に応え、同じ仕組みを市役所窓口で利用し、便利さを体験できるらくらく申請サービスを開始しております。さらに金融機関の協力も得て、カードを持っている人は定期預金や子育て支援の支援ローンの金利で優遇される特典を設け、子育て支援は特に都城市が力を入れている分野で、市の電子母子手帳サービスではマイナンバーカードで本人確認を行い、子供たちの健康診断の結果や予防接種の履歴を提供するサービスもあります。
ほかには、マイナンバーカードを市の図書カードにする環境づくりも進めております。この仕組みなんですが、国のマイキープラットフォームを活用し、マイナンバーカードを活用したマイキープラットフォームでは公共施設の利用者カードを1枚にまとめることが可能になり、市民がボランティアや健康増進の活動を行った場合などに自治体が発行するポイントをマイナンバーカードにもためられます。稲沢の一歩先を走っているのかなと思っております。
先ほどの答弁で、令和3年度から令和4年にかけてマイナンバーカードの交付率が稲沢市も約20%上昇し、愛知県、全国の交付率より上回りましたが、その要因をお尋ねいたします。
◎市民福祉部長(小野達哉君)
令和3年度につきましては、稲沢市の独自の施策として以前から市民課で平日に実施している申請サポートについて休日窓口開庁時にも拡大し、商業施設で月1回実施している申請サポートについてもアピタタウン稲沢を追加いたしました。また、市民センター、中央図書館での申請サポートを新たに実施いたしました。
さらに、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業として、マイナンバーカード普及促進商品券事業を実施したことが大きな要因であると考えられます。この商品券事業では、令和3年6月30日時点で市内に住所を有し、マイナンバーカードを所有、または申請を済ませた方に、いなざわ飲食・商店エール券を1人当たり2,000円分配付いたしました。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。臆測ではありますが、都城市が先行している過程にはマイナンバーカードを作るメリットをたくさん増やしているからだと感じております。1枚のカードで全ての政府サービスが受けられる、そうしたサービスを次から次へとローンチしていけば雰囲気は変わるかもしれないと思っております。
この都城市ですが、市長自らCDO、最高デジタル責任者をやっており、デジタル庁デジタ
ル社会構想会議構成員、内閣官房情報通信技術総合戦略室「デジタルの日」検討委員会構成員もやっており、DXには相当力を入れておられます。外部専門人材もDXアドバイザーとして雇用しております。
これだけテクノロジーが進むとやはり便利なので、稲沢市でもこれを使わない手はないと思います。そのためには、マイナンバーのような国民のデジタルIDを普及させないと話は始まらない。そしてDX人材の雇用も考えていかないといけないと考えます。
○議長(服部猛君)
議事の都合により、暫時休憩いたします。
午前11時39分 休憩
午後1時00分 再開
○議長(服部猛君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
杉山太希君。
◆1番(杉山太希君)
そこで、今年度オンライン使用で募集したワクワクいなざわ応援券について質問いたします。
ワクワクいなざわ応援券を実施したが、1次、2次それぞれの販売実績はどうでしたか、お聞かせください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
本年度、100%のプレミアム付商品券として実施しておりますワクワクいなざわ応援券は、1次販売では、市内全世帯を対象に購入引換券となるはがきを発送いたしました。6月27日から7月31日まで販売し、発送数5万5,901セットに対し、65.2%となる3万6,421セットの販売実績となりました。2次販売では、募集した1万9,480セットに対し、1万9,951人から申込みがあり、当選された方に9月1日から9月30日まで販売を行っております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ワクワクいなざわ応援券の2次販売では、はがきとオンラインでの申込み方法があったが、それぞれ申込み状況を教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
ワクワクいなざわ応援券の2次販売は、1次販売の残数を希望される市民の方が1人1セット申込みができ、当選した方が購入できるものといたしました。官製往復はがきで申し込むか、商品券事業の特設サイトからオンラインにより購入申込みを行う形式としたところ、1万9,951人の方から申込みを受け付け、そのうち1万4,763人、74.0%の方がオンラインによる申込みを選択されました。オンライン申込みはスマートフォンを使用する多くの方にとってより手軽で、はがき購入の負担がない利点がありますが、そのほかに、抽せん結果がはがきより早
期に分かること等を周知したこともあり、オンライン申込みが多かったものと考えております。
◆1番(杉山太希君)
ワクワクいなざわ応援券の2次販売において、オンライン申込みのメリット・デメリット、事業運営における課題は何だったか、教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
ワクワクいなざわ応援券2次販売のオンライン申込みのメリットでございますが、抽せん前に行う入力作業が軽減される点、より早期に当選、落選の結果が報告できる点が上げられます。これらは委託費のコスト削減にもつながります。
一方、デメリットといたしまして、オンラインでの申込みに当たり、入力から販売に至る十分な検証ができなかったこともあり、結果的にスマートフォン等の操作が不慣れな方の中には多くの時間を費やして申し込み、当選、落選の確認もできず、商工会議所、市役所に足を運んで操作方法をお尋ねいただく例も多く発生しております。どうしても解決できない方には商工会議所で手続を経て販売する等対応しておりますが、現状では事業の全てをデジタルで実施することは大変困難であると実感いたしました。
今回の経験から、今後においても紙申込みとオンライン申込みを並行して扱うことが適当と考えておりますが、コストが増大することが課題であると捉えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ワクワクいなざわ応援券の実施に当たり、マイナポイントのようにデジタルのみで事業を実施することは検討したのか、デジタルで実施する場合の商品券印刷等のコスト削減はどうなのか教えてください。
◎経済環境部長(足立和繁君)
本年度のワクワクいなざわ応援券の検討の際には、マイナポイントの仕組みを活用し、対象個人を特定して、申込みにポイントを支給することも検討いたしました。しかし、マイナンバーカードの取得率は5割弱ですが、マイナポイントの申込者は2割程度にとどまっていると推測されましたので、市独自で実施しても広く利用いただける状況にはないと判断いたしました。
商品券の申込みから購入のための入金、店舗の換金までをオンラインで行うデジタル商品券事業を実施する場合、一部の市民が参加困難となるだけでなく、店舗にも新たなキャッシュレス決済システムに参加していただく必要があり、4割から5割の店舗が参加困難となる可能性があります。
全てをデジタルで実施する場合、ワクワクいなざわ応援券に関する事務費では、商品券の入札、引換え販売が不要となるほか、換金の手間が大幅に軽減され、紙面の申込みで発生する確認のための事務作業も軽減されます。このため、事務費予算3,100万円のうち1,200万円程度の軽減を見込むことができます。一方で、システムの利用料等が発生することとなり、これまで
にデジタル商品券の提案を受けるものでは1,000万を超える追加コストとなるものもあり、事務費全体の低減効果は必ずしも大きいものではありません。
デジタルによる消費喚起は、実施の手法によっては一定のコスト低減が期待でき、何よりデジタル対応により事業効果の向上も期待できますので、将来的にはデジタル商品券の実施を模索してまいりたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。私はなんですけれども、デジタル化の大きなメリットとして、人的負担の削減、紙を使用しないことで用紙印刷、郵送などに係る諸経費の削減、プレミアム付商品券が使用されると、いつ、どこで、幾ら使用されたかなどのデータの集計、コロナ禍における非接触決済の実現、この4点かと思っておりましたが、諸経費のほうが、話を聞く限りではデジタル化をしてもあまり減らないのは少し予想外でありました。
今回、デジタル商品券事業を実施する場合に組織、人的負担の面で対応に問題はなかったかお聞きいたします。
◎経済環境部長(足立和繁君)
現在のワクワクいなざわ応援券でオンライン申込みの方から問合せに対応する際、個人のスマートフォンで発生する状況が分からない内容も多く、苦慮するケースが発生しております。商品券事業をこれまで以上にデジタル化する場合には、商工会議所や市の窓口で対応することは困難になると思われます。
デジタル商品券の実施に当たっては、当選者からの入金を受け、店頭での決済を行うために民間のシステムを利用することとなりますが、利用者、店舗のそれぞれからの問合せへの対応もコールセンターを設置して実施することが必要となります。現在の組織、人材のみでは対応は困難と思いますので、委託を行ってまいりたいと思っております。一部の利用者が困難となる問題に加え、導入する決済手段によっては店舗側に事務負担だけでなく決済手数料が発生する場合もございますので、事業全体のバランスを意識して、今後の商品券事業を実施してまいりたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
今回の実施で問題点が浮き彫りになったと感じております。そこで、DX人材が必要だという意見が欲しかったのですが、ちょっと今回は出てこなかったのですが、答弁を聞く限りでは必要だと感じます。
DX人材とは何だというと、私はこの2点だと感じております。
IT技術でできること、できないことの限界を理解し、業務や施策にどのように取り入れられるか柔軟に考えて推進させる能力。データを収集・分析し、市民生活、行政サービス、業務をよりよくするためにどうしたらよいのか住民本位目線で考えられる能力。このデジタル化で
コストはあまり変わらないが、コストの削減方法、削減の解決方法もこういった人材が示してくれるかもしれない、そういった人材がDX人材だと感じております。今後、商品券のデジタル化、市役所全体のデジタル化には私は必須だと思っております。
そこで、デジタル推進課に質問いたします。
令和4年4月に情報推進課からデジタル推進課に名称を改め、各種DXの事業を進めていると思われるが、その際にはDX人材が必要となります。そのため、内部人材を育てたり、外部人材を登用することが考えられますが、まずは内部人材に対する研修などはしているのか、お聞きいたします。
◎市長公室長(浅野隆夫君)
今年度、DX人材を育てるため稲沢市DX推進員設置要綱を制定し、2年間の任期として各部署から主査職以下の職員24名に対し、研修を始めたところでございます。
今年度の研修内容といたしましては、国におけるデジタル化の動きやDXを推進する意義などを伝えるとともに、データ入力など定型的な事務を自動化、省力化するRPA、ロボティック・プロセス・オートメーションの研修を実施し、来年度はDX推進員自らがRPAを作成し、稼働させる研修を予定しております。こうした研修を進めることにより、少しずつではありますが、本市のDX人材が育っていくものと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
DX人材の育成をしていることは分かりましたが、稲沢市のDXをさらに進めるためには外部人材の登用も一緒に考えていく必要があると思います。この外部人材の登用は全国的に進んでいるのか、また稲沢市は外部人材の登用についてどのように考えているのかお聞かせください。
◎市長公室長(浅野隆夫君)
まず初めに、本市のDX化を推進するために副市長を最高情報統括責任者、CIOとしてDXを推進しております。このCIOをサポートするCIO補佐官を外部から登用する自治体も幾つかございますが、国が行ったアンケートによりますと、令和3年9月時点で外部からデジタル人材を任用等している市町村は101団体であり、まだまだ少数となっております。そのため先ほど御答弁いたしましたとおり、まずは内部人材の育成に力を入れ、DX人材を育ててまいりたいと考えております。
また、CIO補佐官をはじめとするDX人材の外部登用につきましては、専門的知見を有し、幅広い経験から指導・助言が受けられるなど、その必要性は感じているものの、求めるべき役割など検討すべきことが多いことから、昨年12月議会で御答弁させていただいたとおり、総務省の人材派遣制度である地域情報化アドバイザー制度を活用しつつ、今後も国や県の動き、他市の状況を見据えてまいりたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。やはり、回答からだと外部人材の登用は市としてやらない方向性なのかなと感じてしまいます。
10万円の定額給付、全国的に遅れが指摘されました。比較的稲沢市は早かったと思いますが、現場の頑張りでやり切ってしまう。中途半端にデジタル化するよりも質の高い職員を活用したほうがいいと考えてしまっているのではないかと感じております。先ほどの商工観光課の答弁も何となくそのような感じがいたしました。
では、DX人材を中途採用しようとした場合どのような手法があるか、月額の給料の幅も教えてください。
◎市長公室長(浅野隆夫君)
職員の採用につきましては、通常の採用のほか任期付任用という手法がございます。任期付任用は、業務上専門的な知識・経験を持った職員が一定の期間必要な場合などに任期を定めて採用するものでございます。任期付任用における特定任期付職員を採用した場合の給料月額は、37万円5,000円から83万円の範囲内で、基準に従い定めることとなっております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。転職サイト等を見ていると、DX人材の求人は40%以上で年収1,000万円以上になっていました。この範囲であればボーナスもつくと思われますので、採用は可能であることが分かりました。あとはデジタル推進課等稲沢市役所が本当に必要とするかどうかの判断だと感じております。
最後に、民から官への人材移動は大きなトレンドとなりつつあります。
1つは、社会の変化の激しさに対応するため今までと違う知見、バックグラウンドを有する人材の必要性が高まってきていることが上げられます。公務員試験なしでの採用、リモート選考の導入、副業オーケーの募集など、民間からの風を受け入れるためにも新しい挑戦を稲沢市に要望して一般質問を終わらせていただきます。
・・・・・・・・・・・・
令和4年3月定例会(3月10日) 映像はこちら
主な内容
1.新型コロナウイルス対策について
(1)コロナ対策費用について
(3)コロナ禍の学校運営について
(4)ワクチン接種について
2.パブリックコメントについて
(1)パブリックコメントの現状について
(2)パブリックコメントの効果について
以下は議事録
◆1番(杉山太希君) (登壇)
皆さん、こんにちは。
議長のお許しをいただきましたので、一般質問を始めさせていただきます。
この場でロシアに45分抗議をしたいところですが、ここは稲沢市。稲沢市の議場であるので、質問席から稲沢市について質問させていただきます。
(降 壇)
新型コロナウイルス対策について聞いていきます。
令和2年度、3年度の一般会計における新型コロナウイルス感染症対策に関わる市独自の事業に要した費用はどれだけかかったんでしょうか。また、そのうち一般財源はどれだけかかったのか教えてください。
◎総務部長(平野裕人君)
一般会計における新型コロナウイルス感染症対策に係る市独自の事業につきましては、令和2年度は高齢者支援商品券事業や小・中学校及び保育園・幼稚園等給食費無償化事業、プレミアム付商品券事業、小規模事業者活性化補助金などがございまして、決算額は4億8,000万円余。そのうち一般財源は2億5,000万円余となったものでございます。
令和3年度につきましては、国が行う給付事業の対象外となった子育て世帯に対する子育て世帯等臨時特別支援事業、マイナンバーカード普及促進商品券事業、高齢者及び障害者支援商品券事業、キャッシュレス決済ポイント還元事業などがございまして、合計7億7,000万円余
を予算計上し、そのうち一般財源は6,000万円余となったものでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
水道料金の値下げも入れれば、市としては結構な費用を使ったのかと感じております。
では、新型コロナウイルス感染症拡大による歳入への影響はどの程度あったのか教えてください。
◎総務部長(平野裕人君)
新型コロナウイルス感染症の拡大が歳入へ与える影響につきましては、国からの緊急経済対策などにより地方創生臨時交付金をはじめ多額の国庫補助金を受けております。令和2年度一般会計決算では、全額国費で負担となった特別定額給付金136億9,700万円をはじめ約157億円の財源を国・県から受け入れており、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費約160億円のうち98%の特定財源が確保されたことにより、一般財源への影響は大きくならなかったものと理解をしております。
加えまして、事業者などに対する継続した国の支援策などにより、市税収入はコロナ禍以前とまでは至っていないものの予算ベースで回復しつつあり、財政的な影響は抑えられているものと思われます。
しかし、コロナ禍の影響による先行きの不透明感は強く、引き続き経済状況を注視していく必要があると考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
新型コロナウイルス感染症の影響などにより先行きが不透明な経済状況が続くと思いますが、今後の予算の在り方についてどのように考えているか教えてください。
◎総務部長(平野裕人君)
今後の経済状況につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に加えて半導体の不足、原油・原材料高やウクライナ情勢の悪化により先行きの不確実性は高い状況にございます。当面はこうした厳しい状況が続く見通しではございますが、稲沢市ステージアッププラン(第6次稲沢市総合計画)の着実な推進に向けて政策効果が高い事業への転換を図るなど、これまで以上に事業の成果を見極め、優先度、必要性を判断するとともに健全財政を安定的に維持するため、市税をはじめとした自主財源の確保に加え、財政的に有利な市債の活用などによる財源の確保にも努めていくことが肝要であると考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
話を聞く限りでは、財務状況はある程度、今現在は安定しているのかなと感じております。国からの経済救済により成り立っているとも感じております。
国の経済救済も、言い換えれば国が肩代わりをして借金をしているだけにすぎないと思って
おります。今後の人口減少やコロナ後のITコストの増加と少子高齢化による社会保障費の増、さらには、これまで公共施設整備に充ててきた起債の返済が長期的に高止まりする中で、その公共施設の老朽化により維持管理費や施設更新経費が必要になり三重苦、四重苦の状況が続いていくと思いますので、楽観的には考えずよろしくお願いいたします。
稲沢市への新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の交付状況はどうでしたか。
◎市長公室長(篠田智徳君)
これまでに国から令和2年度、令和3年度の2か年で総額20億4,490万9,000円の交付限度額が示されており、うち令和2年度事業に11億5,516万7,000円を活用し、令和3年度事業に7億2,510万9,000円、令和4年度事業に1億6,463万3,000円を活用する見込みといたしております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
何の事業に活用したのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
令和2年度におきましては全部で7つの事業に充当いたしており、新型コロナウイルス対策高齢者支援商品券事業、新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業、小規模事業者活性化補助金事業、これはいなざわ事業者げんき補助金でございます。それから新型コロナウイルス対策商品券事業、小・中学校給食費無償化事業、GIGAスクール本庁ネットワーク変更業務、GIGAスクール1人1台タブレット端末整備に活用いたしております。
令和3年度におきましては、マイナンバーカード普及促進商品券事業、新型コロナウイルス対策障害者支援商品券事業、新型コロナウイルス対策高齢者支援商品券事業、公立保育園空気清浄機設置事業、子育て世帯等臨時特別支援事業、これは市単独で行ったものでございます。それから小規模事業者活性化補助金、これはいなざわ事業者げんき補助金でございます。それからキャッシュレス決済ポイント還元事業、あいスタ認証取得促進支援事業、新型コロナウイルス対策農業者応援金交付事業、小学校屋内運動場便所洋式化事業、小・中学校オンライン授業環境整備事業等に充当する予定といたしております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
この臨時交付金を充当した事業の選定理由を教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
臨時交付金を充当した事業につきましては、国への交付金の実績報告あるいは今後の国の会計検査の対応ということなどを鑑み事務負担の軽減を図るということから、新型コロナウイルス感染症対策事業のうちで比較的事業費が小さいものについては臨時交付金を充てずに、なるべく事業費の大きなものの中から充当事業数を絞るといった判断をいたしております。また、対外的に市の取組の独自性をアピールできるかどうかも考慮して判断したものでございます。
以上です。
◆1番(杉山太希君)
財政の方々もこのコロナ禍で相当事務負担が増えているという意見もあり、大変だったと感じておりますが、市は独自性をアピールできたのか、少し疑問には感じております。
臨時交付金を充当した事業の効果はどのようなものであったか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
令和2年度におきましては、交付決定を受けた臨時交付金のうち約70%をGIGAスクール、1人1台タブレット端末整備に充当させていただきました。新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、緊急的に全児童・生徒にタブレット端末を整備する必要がございました。通常の文部科学省の公立学校情報機器整備費補助金だけですと、本市におきましても多額の一般財源が必要となるところ、今回の臨時交付金があったことにより整備を一気呵成に進めることができたことは大変有用であったものと考えております。また、小規模事業者活性化補助金事業、いなざわ事業者げんき補助金におきましては9割以上の執行率、新型コロナウイルス対策商品券事業におきましては9割以上の使用実績となっており、小規模事業者の支援あるいは地域経済の活性化などに効果があったものと考えております。
令和3年度におきましては、新型コロナウイルスの接種率向上が至上命題でございましたが、新型コロナウイルス対策障害者支援商品券事業、あるいは、同じく高齢者支援商品券事業においてワクチン接種会場までの移動が困難な障害者、高齢者の方々にこの商品券をタクシー代としてお使いいただくことも事業目的の一つでございました。消費喚起に加え、そうした方々のワクチン接種会場への交通利便性を高めるとともに交通費の負担軽減を図ることができ、本市のワクチン接種率の向上に寄与したものと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
今回のコロナ対応に関して、地方自治体の中には財政調整基金の取崩しなど損耗が激しい自治体も見られます。稲沢市はさほど取り崩してもおりませんが、次年度以降、今の世界情勢からもさらなる悪化が懸念されています。コロナ禍のような国難においては、短期的には国が責任を持って必要な対策費用を拠出してくれましたが、中長期的には現行の税制も含めて抜本的な改革について稲沢市も議論すべきだと考えております。
そして、コロナ禍という財政のツケ、そして今やらないといけないことを次の世代に先送りすることなく、自分たちの世代で決着をつけていただきたいと思います。もし30年後、私が議員をやっているのか分かりませんが、そのとき財政状況が悲惨であるならば、私は言います。30年前、要望はしたが、加藤市長をはじめ市の幹部の方々が残したと次の世代に伝えます。市としても今だからこそ削るべきは削るという当たり前のことは実行しながら、コロナがあった
からこそ分かってきたこともあると思いますので、今後の対策もよろしくお願いいたしまして、次の質問に移らせていただきます。
学校の運営についてお聞きします。
タブレットの活用計画とオンライン授業の実施に向けた進捗状況を教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
教育委員会では、1人1台タブレットPCの整備に伴い初年度である今年度は学校の指導の負担も考慮して、まずは授業で積極的に活用することを目標としてスタートしております。来年度以降は、より効果的な活用や家庭での活用へと進められるよう計画しております。
オンライン授業につきましては、コロナ禍により早期に実施できるよう環境を整える必要が生じたため、9月下旬から10月上旬にかけて各家庭のインターネット環境調査を実施し、12月議会で関連予算をお認めいただき、来年度からオンライン授業を実施できるよう進めているところでございます。
各学校では、ICT支援員の協力の下、オンライン授業実現に向けて2学期から教員の研修会を実施するとともに、授業の中で児童・生徒がオンライン授業のための操作方法を体験するなどしております。また、タブレットPCの持ち帰りについては、11月中旬から12月上旬に小・中学校1校ずつを持ち帰りモデル校として試行し、その結果を受け1月下旬から2月にかけて各小・中学校においてもタブレットPCの持ち帰りの試行を実施するなど、オンライン授業の実現に向けて進めているところでございます。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
私は、稲沢市のオンライン授業は遅れていると感じておりましたが、オンライン授業開始に当たる準備に力を入れていて、着実に来年度から問題なく始められると解釈いたします。
ガイドラインに沿って授業を進めていると思いますが、各学校の行事の実施に差はあるのか教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
学校の教育活動や行事は特色ある教育活動を進めるようにしておるため、もともと学校間で行事の内容に違いがあることは当然のことであると考えております。コロナ禍で教育活動を進めるに当たり、感染予防のため児童・生徒数や施設設備等の実情に応じて各学校が工夫して進めており、こうした点からも違いは生じていると把握しております。ただし、修学旅行や運動会、学校祭などは全ての学校で実施することができております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
私も周りから、学校によってコロナ対策が違うというのはよく聞いておりました。ガイドラインで締めつけるよりかは特色があってよいと思っております。これからも教育委員会から、
子供たちのこの大切な青春がよりよい方向に進むようお願いいたします。
アフターコロナを見据えて教育委員会の考えはありますか。また、ワクチン接種の有無によって教育活動を工夫していくことは考えているのか教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
教育委員会では、コロナ禍で感染予防対策を講じつつ、学校教育ならではの学びを大事にしながら教育活動を進め、最大限子供たちの健やかな学びを保障することができるよう進めております。そうした中で、各学校はアフターコロナを意識しつつ感染対策を講じながら教育活動を進めているところでございます。
また、ワクチン接種の有無によって教育活動の内容を変更したり差別化したりすることはせず、どの児童・生徒も同様に教育活動を進めていきたいと考えております。そして、新型コロナウイルスによる感染や新型コロナワクチンの接種を受ける、または受けないことによって差別やいじめなどが起きることがないよう十分配慮するように周知しております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
学級閉鎖等が行われておりますが、学習内容は今後終えられるのか教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
各学校では、学習内容は全て終えられる予定で授業を進めております。学級閉鎖等の期間が5日程度から3日程度だったこともあり、現時点では授業の進度に大きく影響するとは考えておりません。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
学級閉鎖等の期間の学習の保障についてはどのように進めているのか。また、陽性者や濃厚接触者になり登校できない状況になったとき、オンラインでの授業参加について対応は可能か教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
各学校では、学習プリントを配付したり電話で健康観察する際に課題を伝えたりして、家庭での学習を進めております。今回の学級閉鎖等におきましては、家庭のWi−Fi環境などの条件がそろっている場合には、タブレットPCを家庭に持ち帰り健康観察で活用した学校も幾つかございます。また、オンライン授業を試行的に実施した学校もございます。教育委員会では、令和4年度以降はオンライン授業が実施できる環境が整いますので、状況に応じてタブレットPCの活用を進めていきたいと考えております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
答弁にもありましたが、プリントを配付するだけになっていたりもすると思いますので、今後環境が整い次第、ハイブリッドでオンライン授業ができるよう要望しておきます。
環境が整った後どう使うかが重要になると思いますので、保護者の意見を聞きながら柔軟に対応のほうもよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、稲沢市内の児童・生徒の体力について変化があったかお聞きします。
◎教育部長(荻須正偉君)
児童・生徒の体力は全国的に低下しております。愛知県については、令和3年度の全国体力・運動能力・運動習慣等調査では、小学校5年生の男女、中学校2年生の男子が全国で最下位、中学校2年生の女子が全国で45位となっております。稲沢市の小・中学生につきましては、全国平均と県平均を上回った種目は小学校5年生の男女の50メートル走、中学校2年生女子の反復横跳び、ソフトボール投げの種目でございました。一方、他の種目については一部の種目で県平均を上回るものもありますが、県平均を下回る種目が多いため、体力全体の合計点については県平均をやや下回りました。
児童・生徒の全国的な体力の低下の背景には、令和元年度から指摘されております運動時間の減少や学習以外のスクリーンタイム、スマホの利用等でございますが、その増加に加え新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けてさらに拍車がかかったと考えられております。特に、新型コロナウイルス感染症の感染防止に伴い学校・家庭での活動が制限されたことで、体育の授業のみならず体力向上の取組自体が減少したと考えております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ちょっと気になったんですが、愛知県については令和3年度の全国体力・運動能力・運動習慣等調査では小学校5年生の男女、中学校2年生の男子が全国で最下位、中学校2年生の女子が45位となっていますと答弁にあります。体力合計点については、稲沢市ですと県平均をやや下回りました。そうなると、稲沢市の子供たちの体力測定は相当低いことになります。このような現状を受けて、今後どのように体力の向上に取り組んでいくのか教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
教育委員会では、この体力テストの結果を基に体力の現状と各学校の取組を把握し、各学校に対して児童・生徒の運動量を確保しながら体力や運動に関する意識を高め、日々の取組に生かすよう指導してまいります。
具体的には、市内の体力づくり優良校の取組やスポーツ実践講座の伝達についての資料を配付し、体力向上に向け周知してまいります。今後は、学校での取組とともに基本的な生活習慣はもちろんのこと、コロナ禍においても日常的に体を動かすよう、家庭と連携を図りながら体力向上に向け取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
学校だけでは解決できない問題でもあるので、家庭との連携を強力にして体力向上できるよ
うお願いいたします。
同様に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって不登校児童・生徒数について変化があったのかお聞きします。
◎教育部長(荻須正偉君)
平成30年度以降、増加傾向が続いております。コロナ前の令和元年度とコロナ禍の令和2年度の不登校児童・生徒数を比較いたしますと、令和元年度が小・中合わせて239名、令和2年度が小・中合わせて243名と4名増加しており、今年度はさらに増加することが予想されております。コロナ禍の影響によって子供たちを取り巻く生活環境は大きく変化し、不安を抱え、ストレス症状が現われたり生活リズムが崩れたりしている子供たちも一部存在し、不登校につながっている現状もあると把握しております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
稲沢市の小学生の児童数で見ると全体で7,185人、中学生が3,535人に対して、中学生の不登校の多さにびっくりしております。データを見る限りですが、コロナ禍では中学生のほうが影響があると感じております。
各学校では、不登校の増加に歯止めをかけるためにどのような取組をしているのか教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
各学校におきましては、不安を抱える児童・生徒や連続して欠席が続く児童・生徒がいる場合は、教師が声をかけたり家庭連絡をしたりするなど本人や保護者に寄り添い、より詳しい本人の状況を把握するよう努めております。また、定期的にケース会議を持つなど心配のある児童・生徒一人一人について複数の教師が情報共有をしております。状況によってはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーにも協力依頼し、心のケアに努めているところでございます。
教育委員会では、今後も新たな一人を出さないためにも魅力ある学校づくりを意識して、日頃から子供たちの変化を見逃すことなく定期的な教育相談等を徹底するなど、組織的に未然防止に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
私も不登校に関していろいろ調べておりましたが、この時代、不登校の原因が多過ぎて教育行政関係者は相当苦労されているのかなと感じます。あと学校教育は、データをいろいろ見ていましたが、本当にちょっと難しいと感じております。例えば、都道府県ごとのいじめですと、児童・生徒1,000人当たりの認知件数では8.9倍の格差が生じています。いじめはどこにでも存在しますが、自治体によってそこまでのばらつきが出ることは考えにくいため、いじめの実態
を表していると考えるのは無理があると思います。いじめに関する事件が起きると、数字が跳ね上がるのも特徴です。大津市中2いじめ自殺事件が起こった後は、すごく顕著でした。同事件は、11年度に約7万件だったいじめ認知件数が、翌年12年度には19万8,000件と増加しました。これは事件が契機となって実際のいじめが2.8倍までに激増したと考えるよりも、事件が児童のアンケートの回答に影響を与えたと見るほうが理にかなっていると思います。つまり、単純に数字だけ追っていじめが増えた、減ったと考えるのは適切ではないとも思っております。
何が言いたいかといいますと、コロナ禍で黙食であったり行事の中止であったりとコミュニケーションを取る機会が減り、いじめがデータ上増えたとしても子供たちがストレス、問題をたくさん抱えているんだと思わず、慎重に現場の声を聞き、稲沢市に合った対策をよろしくお願いいたします。これ以上教師の方々の業務が増えるのも酷ですし、教師の方々が病気になっても困りますので、よろしくお願いいたします。
次の質問に移らせていただきます。
ワクチン接種についての質問になります。
5歳から11歳の小児用ワクチン接種についてお尋ねいたします。
発送は、いつ何をどのように送りましたか。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
5歳から11歳の方につきましては、接種券付予診票、予防接種済証添付用の用紙、新型コロナウイルスワクチン接種の御案内、厚生労働省作成のリーフレット、製薬会社作成の小児用ワクチン説明書の5点を3月1日に郵送しております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
5歳から11歳の小児用のワクチン接種については努力義務ではありませんが、どう対応されていますか。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
5歳から11歳のワクチン接種につきましては、御指摘のとおり努力義務ではございません。このため、同封した厚生労働省作成のリーフレット、小児用ワクチンの説明書などをよくお読みの上、保護者と本人とがよく相談するとともに、基礎疾患のある方はかかりつけ医とも相談をして接種の判断をしていただくようお知らせをしております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
接種は、大人のときのように集団接種をしたり平日に実施をしたりしますか、お尋ねいたします。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
5歳から11歳の方は集団接種を行わず、市内の小児科6か所で個別接種として実施します。実施の日程につきましては、平日を含め医療機関によっては土曜日にも実施されることとなっ
ております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
多分ですけれども、今の状況ですと医者としても判断が分かれているように感じております。かかりつけ医によって判断の差が生じるんではないかと危惧しております。努力義務ではないので何とも言い難いですが、その辺りは6か所の個別接種ということなので、市のほうからもある程度答え方を一致させておいたほうがよいのではないかと感じます。
あと一点、それと全額公費のため病院は打ったほうがもうかるというのもありますので、そこら辺も考慮してお願いいたします。
今まで12歳以上の市民が接種していると思いますが、若い世代、10代、20代、30代の2回目の接種率はどのような状況でしょうか。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
2回目の接種状況としましては、3月7日現在、12歳から19歳までの方は62.9%、20歳から29歳までの方は77.8%、30歳から39歳までの方は80.3%の接種率となっております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
先ほどの答弁で令和3年度におきましては、財政のことなんですけど、新型コロナワクチンの接種率向上が至上命題でございましたとの答弁がありましたが、小児用のワクチン接種については今回は努力義務ではないため、データから、そして昨日の新聞の記事からの予約状況からいくと、50%から70%ぐらいになるのかなと感じております。
今SNS、ユーチューブでワクチン接種で検索してみますと、デマとまではいきませんが情報が錯綜していて、大人が見ても何が本当で何がうそかもよく分からない状況であります。今の時代は、子供たちもSNS、ユーチューブ、何でも情報が取れてしまう状況であります。基礎知識がない状態で情報を取るわけなので、うそをうそであると見抜けないのはとても恐ろしい状況だとも思っております。このワクチン接種からいじめ、不登校につながらないよう十分対策をよろしくお願いいたしまして、次の質問に移らせていただきます。
パブリックコメントについて質問させていただきます。
市民の意見を聞く手法の一つとしてパブリックコメントが上げられるが、どのような経緯から導入されましたか。
◎市長公室長(篠田智徳君)
パブリックコメントにつきましては、平成21年度から実施をいたしております。その導入経緯といたしましては、地方分権が進む中で実効性のある市民参加を推進していく必要があり、市民と市のそれぞれの役割等を明らかにして連携と協働による魅力あるまちづくりに取り組むことが何より重要であることから、平成21年4月1日に稲沢市市民参加条例を施行し、その中
でパブリックコメントも市民参加の手法の一つとして位置づけております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
平成21年度からパブリックコメントを実施しているとの答弁を受けましたが、これまでのパブリックコメントの実施件数等はどれぐらいあったか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
パブリックコメントを開始した平成21年度から令和2年度までの12年間の実績につきましては、パブリックコメントの手続の数といたしましては55件、いただいた意見の件数といたしましては1,005件、パブリックコメントを提出された延べ人数は476人となっております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
パブリックコメントを実施するかどうかの判断は各課で行っているのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
パブリックコメントを含めた市民参加の手続といたしましては、市の基本構想、基本計画、その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定または変更など、市民参加条例第6条に規定する項目に対し市の実施機関は市民参加を求めなければならないものとして、その手法につきましては、市民参加条例に規定する中から各課の判断において計画等の内容に応じた効果的な手法で実施をいたしております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
令和3年6月定例議会において黒田議員から、パブリックコメントの募集時期が毎回年度末に集中しており、市民参加の障害になっているとの一般質問があったが、それに対してどのように対応したか。また、パブリックコメントの意見を受けた後、集約結果を公表する時期が各計画によってばらばらになっていると感じているが、何か理由があるのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
昨年の6月に黒田議員から、一般質問におきまして市民の皆様が意見を出しやすい時期に、またパブリックコメントが重ならないよう早めのスケジュール設定に努める旨の答弁をいたしたところでございます。その旨につきましては庁内へも周知させていただきまして、今年度のパブリックコメントの募集につきましては、一部の案件を12月から募集開始するなど時期を分散させたものでございます。
また、集約結果を公表する時期につきましては、パブリックコメントの意見を集約した結果を内部の会議で調整する場合もあれば、外部の審議会みたいなところで諮る場合もございます。そのため、計画等の種類によっては公表までの時間を要するものがございます。ということで時期がずれるということでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
パブリックコメントに関して提出できる対象者の条件はあるのか。例えば、本市に隣接する市外住民でもコメントできるのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
パブリックコメントを提出できる対象者につきましては稲沢市民に限るものとし、市民参加条例第2条第1号におきまして、市民とは市内に在住、在勤または在学する個人並びに市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体と定義をいたしております。パブリックコメント等の市民参加の趣旨として、市民が施策等の企画、立案、実施及び評価のそれぞれの過程において市民参加を促すものであるため、稲沢市内に在勤、在学していない市外在住の方からの意見については受け付けていないという状況でございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
パブリックコメントを提出できる条件に当てはまるかを確認するため、市として市内在住、在勤、在学かどうかの本人確認は実施しておりますか。
◎市長公室長(篠田智徳君)
パブリックコメントを受け付ける際には、提出する方が本市に在住、在勤、在学等していることを明らかにするために住所あるいは氏名等を記載して提出いただいておりますけれども、実際の事務手続としては、それを基に住基情報と照らし合わせて本人確認をするというところまでは行っておりません。以上です。
◆1番(杉山太希君)
計画等に反対するために、1人が複数の人に成り済まして複数の意見を出したり、市外住民が偽名を使い市民として意見をしたりすることも考えられるが、市としてどう取り扱っているのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
なりすまし等はないものと考えておりますが、仮に同一人物が複数人の名前や住所を偽って同じ内容の意見を複数人分と提出したといたしましても、同じ内容の意見については1つの意見ということで集約し、その意見に対して1つの回答を作成するという取扱いを行っております。
そもそも、パブリックコメントにつきましては、計画等に対する賛成、あるいは反対を表明するものではなくて計画等に対する意見、あるいは課題、問題、情報などをいただいて政策形成に反映していくという制度だと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
黒田議員の一般質問の答弁で、意見の数は関心の高さとも答えておりましたので、気になっておりました。
それはさておき、市としては情報データを軽く見ているのかなと思っております。例えばで
すが、セブンイレブンでは値引きをしておりません。なぜなら、POSデータが狂ってしまうからです。何かといいますと、本来来るべき行動データ、心理データが取れなくなってしまう。トレンドについていけなくなってしまうんです。需要予測が落ちて、値引き販売頼りの過剰発注だったり、データがないと全国の店舗にアドバイスができない。だから値引きをしないのです。データは大切なんです。
今回約12年、手続数は55件、件数は1,005件、パブリックコメントを提出された延べ人数476人となっております。これだけの膨大な情報データが取れたわけでありますが、あまり生かされていないように感じます。意見者は、名前、住所、勤務先、学校しか書く欄がありませんが、住基情報と照らし合わせ等をしていれば誰が何歳でどんな人物、男性・女性、同じ人は何回意見してきたのかを、ここら辺から波及してSNS、LINEで募集したならば新規でこの層から意見がもらえる。今後の新規市民参加のやり方、いろいろつかめたはずではないのでしょうか。これから先パブリックコメントを使うのであれば、データ分析を積極的に進めることを要望いたします。
提出されたパブリックコメントの内容についての傾向を教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
パブリックコメントの内容につきましては全てを明確に分析できるものではございませんが、その意見の内容につきましては、質問や感想を記したもの、あるいは賛否のみを表記するもの、それからパブリックコメント制度そのものに対する御意見など様々なものがございます。その中でも施設の統廃合を進めるような市民に直接的な影響を及ぼす計画に対するパブリックコメントにつきましては、比較的その内容に対し反対の意見を述べるものが多いように感じております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
令和2年度に提出されたパブリックコメントの意見に対して、実際に計画等に意見を取り入れた件数、割合、また具体的な事例はどのようなものがあったか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
令和2年度のパブリックコメントにつきましては、12件の手続におきまして329件の意見が提出され、そのうち次期男女共同参画プラン策定事業、稲沢市ホタル保護条例の制定、稲沢市立保育園再編計画、稲沢市ごみ処理基本計画(改定計画)策定事業、投票区・投票所再編(案)の5件の手続におきまして、19の意見を各計画に取り入れました。よって、令和2年度にパブリックコメントの意見を計画等に取り入れた割合でいたしますと約5.8%となります。
また、意見を取り入れた具体的な事例といたしましては、投票区・投票所再編(案)の中で、一部地域におきまして投票区の区割りを既存の小学校区を基準としていたところをパブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ、地域の実情に合わせた区割りといたした例もございます。
以上です。
◆1番(杉山太希君)
この5.8%は大きい数字ではあると思いますが、見ている限りですと、図をいじるだけであったり間違いを直すだけだったものも多い気がしております。現行のパブリックコメント募集の方法では一部の市民からしか意見が提出されず、また計画等にも反映されにくいのが現状ではないでしょうか。そのため、パブリックコメント以外の市民参加の手法も取り入れ、もっと広く意見を聞くべきではないでしょうか。
◎市長公室長(篠田智徳君)
パブリックコメント手続につきましては、一部の市民からしか意見が提出されない例も見受けられることを踏まえ、例えば今年度に実施いたしました稲沢市公共施設等総合管理計画改定案の意見募集の際には、計画改定案の本体はもちろんですが、概要版も作成し公開するなど、市民がその内容を理解しやすいように努め、これまで意見を提出したことがない方も参加しやすいような工夫を試みているところでございます。
今後、パブリックコメントの手法に限らず、特に策定期間の長い計画等につきましては、ワークショップなどの市民の皆様の声を直接聞く手法、手法といいますか、手続や審議会や公聴会等、他の手続も複合的に実施するとともに新たな手法も研究するなど市民参加の機会を増やすことで市民と市との協働を推進し、魅力ある稲沢市の実現に近づけるよう今後も取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
最後に、これは私の推測として聞いてください。
パブリックコメントについての意見ですが、ほとんど考慮、反映されていないと推測しています。といいますか考慮、反映ができない、あるいはその必要性もないと言ったほうが適切なのかもしれません。
意見提出を受けた行政は全ての意見に目を通し、パターン化した上で整理、件数統計や意見に対する考えを作成、公表します。そして多数意見、あるいは的確と考えられる意見を反映させるなど変更修正を行うことが想定されているのですが、そのようなことは次のような理由からほぼ不可能、あり得ないと思っております。
原案であるA案に対して肯定意見、アンチあるいは対案が提出された場合を想定してください。圧倒的にアンチあるいは対案が多ければどうなるでしょうか。もしこのような結果になれば、A案という原案を廃案あるいは対案に変更することは十分あり得ると推測します。しかしながら、現在の行政機関は世論というものを過剰なまでに意識して各種計画や法を立案していると思いますので、このような状況になることはまずあり得ないものと考えます。
さらに言うと、原案の作成過程では、数々のオプションや予測される反対意見に対して行政等の内部で十分議論を行った上で成案としていますので……。
○議長(服部猛君)
杉山議員、時間が来ました。
◆1番(杉山太希君)
はい。
以上で一般質問を終わらせていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和3年12月定例会(12月10日) 映像はこちら
主な内容
1.稲沢市公共施設等総合管理計画について
(1)稲沢市公共施設等総合管理計画の現状と取り組みの方向性について
(2)人口減少による小中学校の今後について
(3)市道の更新費用について
(4)上水道と下水道のコストと管路更新の考えと状況について
2.「子育て、教育は稲沢で!」について
(1)子育て支援の現状と今後について
(2)子どもの医療費について
以下は議事録
◆1番(杉山太希君) (登壇)
皆さん、おはようございます。
服部議長より発言のお許しをいただきましたので、発言させていただきます。
今日の人口減少、少子高齢化の進展、地方財政の状況などを勘案すれば、公共施設などの見直しは必至であり、政策的な対応が求められます。問題は、その中身、進め方だと思っております。この議場にいる中で、確率論でいけば私が今後一番長く生きると感じております。だからこそ、この稲沢市公共施設等総合計画、何十年というスパンの計画なので、質問させていただきます。これ以降は質問席にて発言をさせていただきます。
(降 壇)
現在、企画政策課において改訂作業を進めている稲沢市公共施設等総合管理計画の改訂案の中に施設関連費の推移が掲載されているが、2017年度以降、その金額が増加傾向にあります。これはもともとの合併特例債の発行期限が2020年度であったことから、そこに向けて計画的に施設整備を進めてきたことが原因だと思われますが、今後5年間はどのように推移するか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
現在では、合併特例債の発行期限は2025年まで再延長しておりますが、議員のおっしゃるとおり再延長前の発行期限であった2020年、令和2年度に向けて施設整備が集中した背景がございますので、施設管理経費が伸びております。
今後につきましては、井之口の給食調理場などの建設計画があるものの、用途廃止済みの施設の除却も複数控えておりまして、施設総量とともに維持管理や更新等に関する経費は減少するものと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
計画の改訂案に示されている従来型の箱物費用推計を見ると、過去の施設関連経費の平均が46.4億円であるのに対し、2020年度以降、数年にわたり120億円前後の費用が必要となってくるが、どう対処していくのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
従来型による費用推計を受けまして、計画改訂案の中で予防保全の考え方による長寿命化型の費用推計を行っております。従来型が建築後20年で大規模改造を行い、40年後に建て替える想定であったのに対しまして、長寿命化型は建築後20年で大規模改造、40年後に長寿命化改修を、60年後に大規模改造を行うということで、建物をよい状態に保ちながら80年間もたせるというものでございまして、それにより費用の平準化を図っております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
私は、この長寿命化は後の世代に先送りしている気がして少し嫌いなのですが、長寿命化を図ったとしても、結果として不足分が発生しているが、どう対処していくのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
施設の集約化や複合化を積極的に進めるとともに、改築する場合においても必要最小限の施設規模にとどめるなど施設総量の適正化に努めるほか、より効率的で効果的な施設の運営、整備を実現するために、民間活力の導入なども図っていきたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ほかの自治体の公共施設総合管理計画を見ると、箱物の延べ床面積の15%から30%程度の縮小を目標に掲げていることが多いです。
神奈川県相模原市の公共施設の公共施設白書は、施設の床面積で80%まで削減することは、市内の全ての行政施設と市民文化施設、生涯学習施設、スポーツ・レク施設を廃止するということに相当すると述べております。20%削減というのはそういう水準ですが、稲沢市の場合はどうでしょうか。
◎市長公室長(篠田智徳君)
稲沢市におきましては、公共施設に係る更新等の費用の不足額を縮減目標といたしておりま
す。議員おっしゃられた多くのほかの自治体のケースで見られる延べ床面積ではなくてコストによる縮減目標を掲げた理由でございますが、公共施設の再編におきましては、施設の廃止・解体ありきではなく、必要な公共サービスをいかに効率的に提供するかという視点が重要であったことから、短絡的に施設の総量のみにフォーカスを絞った目標ではそういった経営の視点が抜け落ちてしまうという懸念があったため、このような目標を立たせていただいたものでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
さすがは稲沢市だなと感じました。ありがとうございます。
計画の改訂案の中に、今後の財政状況については大変厳しいことが想定されますとあるが、この直近5年間、延べ床面積はほぼ横ばい、そして施設に関しては16施設増加しております。具体的にはどのような施設を再編の対象とするのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
高齢化の進展等による扶助費等の社会保障関係経費の増加が見込まれる一方で、交付税の合併算定替えが終了し、また合併特例債も残り僅かという状態でございます。今後も人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響により税収の減少が見込まれます。そういった財政状況にあって待ったなしの状態である公共施設の老朽化がそれに拍車をかけているというような状況でございます。同じような機能を持つ施設が複数あるものについては集約化を、また近接地に幾つかの施設が散らばっている場合は複合化を積極的に進めるとともに、民間事業者に委ねることにより、より効率的な運営や質の高いサービスの提供が期待できる施設については民間活力の導入を図ってまいりたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
積極的に施設の統廃合等を行っていくのであれば、もっと具体的な計画を策定していくべきだと思うのですが、どうでしょうか。
◎市長公室長(篠田智徳君)
今回の稲沢市公共施設等総合管理計画の改訂の中で、今後取り組むべき公共施設の再編として、個別の施設名を上げた上で短期的、中期的な取組を掲載させていただいており、できる限り具体的な計画となるよう努めているところでございます。個々の施設の性格に応じ、事業化する時期を見定めながら丁寧に議論を進めていくべきと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
この計画は、まだ住民、市民には十分周知されておらず、その狙い、目的、内容を早急に知らせ、学習していくことが大切だと感じております。また、住民自らが地域や暮らしの実態、公共施設の配置状況、利用実態、管理運営の在り方などを調査・検討し、課題を明らかにして
改善策を提案していくことも要望いたします。
現在、稲沢市公共施設等総合管理計画の改訂案のパブリックコメントを実施しているが、2017年3月に当初の計画策定の際に実施されたパブリックコメントでは、どのような意見が寄せられたか、またどのような意見が計画に反映されたか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
当初つくりました稲沢市公共施設等総合管理計画の策定に当たりましては、平成29年2月7日から3月6日までパブリックコメントを実施し、6名の方から合計で39件の御意見をいただいております。
寄せられた意見といたしましては、人口や財政の見通しにおける数値や更新費用の推計手法、試算結果に対し説明を求めるもの、また個別の施設の存続等に対する要望がほとんどでございましたので、計画に反映させるには至っていないものでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
私もコメントを全て見ましたが、このパブリックコメントというのはあまり意味がない気がしております。
長野県飯田市では、各地区に地域別検討会議が設置され、地域が主体的に検討し、在り方を決めています。そこでは地域の自治力の発揮、自主的・自立的な運営、行政との協働が基礎になっているようです。
計画をつくってから意見を聞くのではなく、稲沢市も飯田市のような検討会議を重ねてから具体的な計画を立てていくようお願いいたします。
次の質問に移らせていただきます。
公共施設の保有状況では、学校の総延べ床面積が53%と半分以上の割合を占めていますが、このことに対する教育委員会の認識をお願いいたします。
◎教育部長(荻須正偉君)
普通会計における公共施設数は287施設あります。そのうち学校は32施設で、施設数の割合としては11.1%となりますが、1校当たりの延べ床面積が大きいために、市内公共施設の総延べ床面積の保有割合に影響しているものと考えております。
また、総延べ床面積の半分以上を占める学校の施設につきましては、本市の特徴として市街化調整区域に多くの集落が点在しており、コミュニティーごとに建設された学校が存在していることと、団塊ジュニア世代をピークとする児童・生徒数の増加に伴い、学校を新設した結果であると認識しております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
現在、少子高齢化が進み、児童・生徒数は減少していると思いますが、10年前と比較して児童・生徒数はどのようになっているかお尋ねいたします。
◎教育部長(荻須正偉君)
平成23年度の児童・生徒数は1万2,116人であり、今年度の児童・生徒数は1万720人で、1,396人減少しております。減少率といたしまして11.5%となっております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
人口減少に伴い、子供の数も減少しており、学校の統廃合は今後避けては通れない課題でもあると考えます。小規模校は1学年1学級のためクラス替えもできず、子供同士の関係が固定されるため、問題が起きるとこじれやすいと言われております。また、運動会など学校の行事も盛り上がりに欠け、学校全体に活気がない。授業などの教育面では、子供一人一人に教員の目が届くのが小規模校のメリットですが、人数が少な過ぎると逆に教育効果が低下するという研究結果もあります。1学年1クラスの小学校が23校中10校ある現状をどう思っているのかお尋ねいたします。
◎教育部長(荻須正偉君)
平成26年度に教育委員会がまとめました稲沢市の義務教育と学校のあるべき姿の指針を踏まえ、将来を担う子供たちに活力ある教育活動を展開するためにも、学校規模の標準規模化は必要であり、小規模校の再編は必要であると考えております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
小規模校の再編は必要であるとのことですが、稲沢市では、老朽化した施設の長寿命化工事を実施していく学校は再編の対象外となるのかもお尋ねいたします。
◎教育部長(荻須正偉君)
現在、本市の学校施設は老朽化対策のため長寿命化工事を実施していく計画ですが、今後学校再編を検討していく中で存続予定の学校は長寿命化工事を実施し、再編予定の学校は施設維持のための必要最小限の部位補修を行うなど、学校再編と長寿命化工事との整合性を図っていきたいと考えております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
それでは、小規模学校の再編が今まで進んでいない理由は何か教えてください。
◎教育部長(荻須正偉君)
小規模校の再編が進んでいない大きな理由といたしましては、母校がなくなることに対する反対意見が大きいことがございます。加えて、下津陸田区画整理事業による人口増加に伴い、過大規模校となる下津小学校と治郎丸中学校の通学区域再編、普通教室への空調設備設置、GIGAスクール構想による校内LAN整備などの多くの事業を進める必要があったことによるものでございます。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
大変労力を有する事業なのはすごく分かります。私もそうですが、児童・生徒とその保護者、卒業生、地域住民などにとって自分たちの学校がなくなるのは大問題であると考えております。やはり自分の通っていた学校がなくなるのはすごく悲しいです。
一方で、その学校に愛着も利害もない者にとって、在校児童・生徒の数に比べてはるかに大きな敷地や建物の維持費、そして教員の人件費など財政支出は無駄以外の何物でもなく、統合反対を唱える人は自分たちの利益を優先するように映るかもしれないです。ここにも学校統廃合問題の難しさがあると感じております。
稲沢市公共施設等総合管理計画の改訂を受けて、今後どのように取り組んでいくのか市長にお尋ねいたします。
◎市長(加藤錠司郎君)
現在改訂中の公共施設等総合管理計画の案には、今後取り組むべき公共施設の再編の中に、小・中学校については2027年度以降、学校再編・校区再編について検討実施となっており、実施という文言もございます。検討段階で住民からの反対意見が出て議論が進まなかった過去の事案もありますので、学校再編・校区再編につきましては慎重に進める必要があると考えておりますが、将来的な児童・生徒数の減少を見据え、また施設の老朽化対策という喫緊の課題もある中で再編計画の策定も視野に入れて議論を重ね、検討していく必要があると考えております。
◆1番(杉山太希君)
統合に関しては、メリット・デメリット、たくさんあるとも感じております。
最後に、最も重要なのが保護者の意向だと思っております。未就学児の保護者を含め、統廃合に対する賛否や考え方の意向などを教育委員会がアンケート方式で調査するなど、判断材料を増やす取組は考えられないでしょうか。
他市のアンケート調査を何件か見ましたが、統合に賛成は10%前後、やむを得ないは60%前後、反対は10%ぐらいにおおむねなっておりました。保護者の方は、ある程度覚悟はしているような気はしております。心身に負担はかかると思いますが、小さなことからでもよいので少しずつ前に進めていただくよう要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。
現在、市が管理している道路総延長を教えてください。
◎建設部長(鈴森泰和君)
現在、市が管理しております道路総延長は約1,720キロメートルでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
2017年3月に策定した稲沢市公共施設等総合管理計画と今年度末に改訂予定の道路延長を比べると、この5年間で約6キロ弱増えていますが、増えた要因を教えてください。
◎建設部長(鈴森泰和君)
道路の実延長が増えた主な要因といたしましては、県道付け替え整備の完了に伴い、これまで愛知県が管理していた県道を市道へ降格したことや、民間の開発行為に伴う道路の帰属などにより、市が管理する道路延長が増えたものでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
県道から市道への降格が主な要因とのことですが、今後も同様なことがあるのでしょうか。あるのならば、今現在分かる範囲で教えてください。
◎建設部長(鈴森泰和君)
主要地方道名古屋祖父江線の一色市場町地内にあります国道155号との交差点、片原一色交差点でございますが、これから梅須賀町地内にあります主要地方道一宮蟹江線、西尾張中央道との交差点、梅須賀交差点までの区間におきまして、南側にバイパス道路として県道馬飼井堀線と主要地方道名古屋祖父江線の整備が完了しております。
現在、愛知県が施工しております儀長町地内の2級河川三宅川に架かります正楽橋の架け替え工事が完了いたしますと、この県道から市道への降格がされる予定となっております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
今年度末に改訂される稲沢市公共施設等総合管理計画によると、道路における今後35年間の更新費用の総額が672億円となっており、1年当たり平均した場合、19.2億の費用が必要となります。また、更新費用に関しても、今後35年間で総額81.8億円となっており、1年当たりに平均した場合、2.3億円の費用が必要となります。今後、実際に年間どのぐらいの更新費用が必要なのか教えてください。
◎建設部長(鈴森泰和君)
現在、道路につきましては、令和2年度に策定いたしました稲沢市舗装長寿命化修繕計画に基づき、市が管理する主要幹線である1・2級市道の舗装の更新を行っております。
今後10年間の費用につきましては、本計画上では約31億円必要とされており、1年当たりに平均した場合、約3億1,000万円の費用が必要となります。
また、その他市道となります生活道路の更新につきましては、毎年、地元行政区から提出されます要望書により、側溝の改修や舗装整備を行っておりますが、近年の費用につきましては、1年当たり約5億円でございます。
次に、橋梁に関しましては、現在橋梁更新計画ではなく、稲沢市橋梁長寿命化修繕計画に基づき補修を行っております。この計画は、橋梁に大きな損傷が発生してからの修繕、架け替え、いわゆる事後保全型ではなく、定期的な点検による損傷の早期発見、早期の対策を実施する予防保全型により、全体的な補修費用を抑制し、老朽化が進む多くの橋梁を適正に維持管理していくことを目的としております。
なお、この修繕に要する費用につきましては、1年当たりに平均した場合、約3億円が必要となります。以上です。
◆1番(杉山太希君)
道路の更新費用の見込みが公共施設等総合管理計画と比較すると大きく乖離しております。この計画の道路の更新費用はどのように推計しているのか教えてください。
◎市長公室長(篠田智徳君)
今回の公共施設等総合管理計画における道路の更新費用につきましては、総務省の公共施設等更新費用試算ソフトを用いて試算をさせていただきました。この試算ソフトにおきましては、単純に道路の総面積に更新単価を乗じることで費用の総額を推計し、そこから1年当たりの費用を算出する仕様となっております。
こちらを活用した理由といたしましては、道路は路線ごとに一度に整備するのではなく、区間ごとに整備していくことから、年度別にどれだけの費用が必要かを把握することが困難であるためでございます。杉山議員御指摘の課題があることは認識をしておりますが、ほかに代替の手段がないため、この試算方法を採用させていただいたものでございます。御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
◆1番(杉山太希君)
年度ごとで費用把握が困難であるため、総務省の試算ソフトにおいて推計したとのことで致し方ない部分はあると考えますが、計画数値と実態とがこれだけかけ離れているのは好ましくないのではないかと思っております。次回以降、計画を改訂する際、もう少し実態に沿った金額を示せるよう工夫していただくことを要望して、次の質問に移らせていただきます。
本市では、上水と下水道に関しても膨大な施設を保有しております。当計画上では、上水道・下水道に関わる維持更新に関しても、今後多くの費用が必要とされることが懸念されます。市の財政上、実際に適切な事業運営が可能なのでしょうか、お考えをお聞かせください。
◎上下水道部長(村田剛君)
本市の水道事業の維持更新につきましては、漏水等の事故発生率も考慮いたしまして、適切な更新時期を設定し進めております。さらに、その更新に当たりましては、更新する水道管路に長期間使用できる管材、材料でございます、これを採用すること等によりまして更新費用の縮減を図っております。
また、維持更新の財源につきましては、水道の使用料収入の見込みに加えまして、国等からの補助金を最大限に活用するとともに、アセットマネジメントの手法を採用いたしまして、維持管理費用の平準化を図ることにより、安定した事業運営に努めてまいります。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
下水道施設に関しては、現状においても一般会計から多くの費用を支出している状況だと思います。今後の施設の維持更新においても多くの費用が発生するかと思いますが、どのように考えているのかお聞かせください。
◎上下水道部長(村田剛君)
本市の公共下水道は平成12年度より供用開始いたしておりまして、比較的施設が新しいこともあり、維持更新費用につきましては、まだあまり多くは発生しておりません。しかし、現在は新規の整備に注力いたしまして進めておりますため、多くの整備費用を要しております。この整備が一区切りした後は、整備費用の抑制に加えまして、引き続き下水道へのお客様の接続率を向上し、使用料収入を増加させることによりまして、現在よりも収支バランスは好転するものと考えております。
しかし、御指摘のとおり、今後は施設の老朽化等に備えるための多くの維持更新費用が必要となることが想定されます。このため、将来の大幅な費用増大を防ぐために、施設の適切な点検や維持更新等によりまして、計画的に長寿命化、さらに耐震化を併せまして図ってまいります。このような予防保全の徹底が施設の健全性を確保するとともに、ライフサイクルコストの縮減につながるものと考えております。
また、この維持更新に要する費用につきましては、下水道の使用料に加えまして、国・県からの補助金等を最大限に確保することにより、一般会計からの補助の負担軽減を図りながら安定した事業運営に努めてまいります。
いずれにしましても、先ほどの上水道、さらに今の下水道ともに重要なライフラインを今後も長期にわたり安心して使っていただけますよう、計画的な維持更新により健全な事業運営を行ってまいります。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
上下水道もつくる時代、使う時代を経て、もたせる時代になったと思っております。
また、調査技術、維持管理、補修・更新技術ともに研究開発の途上にあるため、情報にアンテナを張り、コスト削減の意識を持ってこれからもよろしくお願いいたします。
最後に、施設を造るときは皆さん喜んでいただけるのですが、統合したりなくしたりするときは皆さん猛反対です。ですが、今後は増やすことがよかった時代から減らすことがよいとする時代、そういった雰囲気づくりも重ねて要望し、次の質問に移らせていただきます。
今の子育て支援の現状について、どのような取組がされているか、また今後についてはどのように取り組んでいくのか教えてください。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
子育て分野における本市の取組につきましては、子育て応援アプリとウェブサイト「すくすくいなッピー」による子育て世帯への速やかな情報発信や、子育て支援センター、児童館、児童センターなど子供や親子にとって快適で安全な居場所の提供、そのほか相談事業、子供の見守り支援など幅広い事業に取り組んでおります。
また、保育におきましては、子育て世帯の負担軽減のため、保育園・幼稚園の給食費の補助や第3子以降の保育料の無償化を実施するなど、子育てしやすい環境づくりに取り組んでおります。
今後につきましては、来年度以降、多胎児支援についての取組を進めたいと考えており、引き続き子供たちや保護者に寄り添った支援ができるよう、子育て支援施策の推進に努めてまいります。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
「子育て・教育は稲沢で!」のキャッチフレーズは、市民の皆さんにすごく定着しております。同級生がみんな子育て世代になる中、毎回この言葉を言ってくれるのですが、稲沢市ではこれがすごいと胸を張って言いたいので、これからもよろしくお願いいたします。
今、国で実施することが決定している18歳以下の子供のいる世帯に対する10万円相当の給付事業についてお聞きします。
現段階での状況を教えてください。
◎子ども健康部長(水谷豊君)
18歳以下の子供に対する1人当たり10万円相当の給付事業である子育て世帯等臨時特別支援事業につきましては、まずは現金5万円を先行して給付し、その後、5万円分のクーポンを配付することとされております。
稲沢市では、5万円の先行給付金については、公務員を除く児童手当受給者に対しては12月中に、そのほかの対象者に対しては1月以降申請を受け付け、順次給付していく計画としています。
クーポンの配付については、いろいろな手法が国から示されてきており、自治体ごとに対応を考えることとされております。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
静岡県島田市は、現金給付を望む子育て層の声が多く、コロナ禍でクーポン受け渡しのときの負担にも配慮したとして、10万円全てを現金で給付する方針を既に発表しております。
市長にお尋ねいたします。
地方の声を国に届けるという意味で、稲沢市も国から牽制されるかもしれませんが、10万円
現金給付を発表できないでしょうか。これだけ話題になっていることから、稲沢市の宣伝にもなると思うのですが、市長の見解もお尋ねいたします。
◎市長(加藤錠司郎君)
杉山議員におかれましては一番若い議員ということで、将来にわたって稲沢市の公共施設の在り方や子育てについて責任を持ってこれからも議論をいただきますようによろしくお願い申し上げまして、まず答弁をさせていただきます。
18歳以下の子育て世帯臨時特別支援事業につきましては、先ほど部長が申し上げましたように、まず5万円の現金給付について、年内の支給に向けて準備を進めているところでございます。また、残りの5万円をクーポンにするかどうかという点につきましては、毎日非常に大きな議論がされていますし、国の考え方も実はまだあまりはっきりしていないというような状況です。昨日も愛知県市長会から、今の制度設計では基本的にはクーポンだと。そして、特例的に現金給付を認めてもいいというようなことで、現金給付はあくまでも特例だというような言い方をしております。愛知県市長会は、これに対しまして、市町村が独自でこれを決められるようにしてくださいという要望書を昨日提出しております。
その中で、私の考えを今から申し上げます。まず、昨年の一人一律10万円の給付金のときに、これが貯蓄に回ってしまったという大きな反省点がございました。そういった点で、岸田総理も言っておりますように、政策のもともとの意味として、貯蓄に回らないということ、そして民間事業者の振興にもなるということ、それから新たな子育てサービスを創出するという点、それから消費の下支えと、こういったことを上げております。その根底には、先ほど言ったように昨年の反省があるということでありますので、私といたしましては、基本的には5万円はクーポンでの制度設計を急ぎたいというふうに考えております。
今後、今日も新聞に報道がありましたように、じゃあいつまでクーポンを使えるようにしたらいいかということがございますので、これがあまりにもタイトで職員の事務量も多くなるというようでしたら、現金給付ということも考えたいと思いますけれども、基本的には、先ほど申しましたように、私はクーポンで行いたいと今のところ考えております。ただ、様々な理由で現金給付に変えることもあるかも分からないというのが今の状況です。
いずれにしましても、国の言っていることも毎日のように変わっておりますので、その中で、稲沢市にとって、子育て世代の利益になって、なおかつ稲沢市内で経済が循環をして消費の下支えになるような、そういったものにしていきたいというふうに考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
国の予算であるため、国の動きに注視しながら臨機応変な対応をよろしくお願いいたします。
次の質問に移らせていただきます。
愛知県内において、入院・通院ともに高校生まで無料化している自治体はどれだけあるのか教えてください。
◎市民福祉部長(小野達哉君)
県の調査によりますと、令和3年10日1日現在、入院医療費、通院医療費ともに高校生まで無料化している自治体は、北名古屋市をはじめ9市町村となっています。また、既に公表されておりますとおり、令和4年1月診療分から名古屋市が、令和4年4月診療分から岩倉市と弥富市が高校生までの医療費を無料化いたします。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
稲沢市が高校生の通院まで医療費無料化を行った場合、どれぐらい費用がかかるのか教えてください。
◎市民福祉部長(小野達哉君)
まず、準備に係る費用といたしまして、システム改修を含めた事務費が1,200万円ほどかかります。また、無料化を開始してから毎年扶助費などが1億2,000万円ほどかかると見込んでおります。
以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
先ほどの答弁にもございましたが、県内では、高校生までの通院医療費まで助成を拡大する自治体が増えております。財政的に厳しい状況でありますが、「子育て・教育は稲沢で!」を掲げる稲沢市においても、高校生の医療費の無料化を実施するべきではないでしょうか。
また、子育て世帯の経済的負担の軽減という視点でいいますと、来年度から国民健康保険税の未就学児の均等割が5割軽減されると聞いております。子育て世帯にとっては大きな負担軽減となる制度だと思いますが、さらなる子育て支援策として、子供の均等割減額の対象を拡大するなどの考えはないでしょうか、市長にお伺いいたします。
◎市長(加藤錠司郎君)
高校生等の医療費につきましては、令和2年、去年の8月から入院医療費を無料にしたところでございますが、さらなる子育て支援の拡充を図るため、通院医療費についても無料化を行っていきたいと考えております。
ただ、実施時期でございますが、基本的には令和5年、再来年の4月からの開始を考えております。この時期とする理由といたしましては、福祉医療のシステムが令和5年4月に更新時期を迎えるということ、また受給者証の有効期限が3月末日まであるということによって、簡単に言うと、中学校3年生の子供がそのまま高校1年生になりますので、この分の事務手数料
が4月からにすると省けるということがございます。こういった点でシステムの改修費や受給者証更新等の事務量を削減できるということがございますので、ちょっと今からやっても来年の4月からは難しい点がございますので、もう一年、誠に申し訳ないんですが、入院の費用について昨年やりましたので、令和5年4月の開始としたいというふうに考えております。
またなお、関連いたします条例の改正案を来年の12月議会に上程する予定でございますので、よろしくお願いいたします。
次に、国保税の均等割についてでございますが、子供を含めて世帯の加入人数が多くなるほど税額が増えることになります制度上、国民健康保険の負担が重く感じる要因の一つとなっております。こうした中で、国保に加入する子育て世帯の負担を軽減するため、国の制度である未就学児の軽減に加え、稲沢市独自の施策として、来年度から高校生までの均等割につきましても5割軽減する方向で、その財源も含めて今は調整を進めているところでございますので、よろしくお願いいたします。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
現状でも、「子育て・教育は稲沢で!」と私も言っておりますが、もっと声を上げて市外・市内の同世代、子育て世帯の方々に子育て・教育は稲沢市でと伝えてまいります。
以上で、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和3年6月定例会(6月17日) 映像はこちら
主な内容
1.農業の現状と課題について
(1)農家人口と専業農家及び兼業農家の数の推移について
(2)農地の地目別経営耕地別面積について
(3)農産品の品目別生産額と販売金額規模別農家数の推移について
(4)耕作放棄地の状況について
(5)農業の後継者について
2.防災について
(1)非常食の備蓄の現状について
(2)農業と非常食の親和性について
以下は議事録
◆1番(杉山太希君) (登壇)
皆様、おはようございます。
ただいま木村議長に発言のお許しをいただきましたので、発言させていただきます。
Jアラートが10時に鳴るということで、大変緊張しております。御託を並べるとJアラートが鳴ってしまうかもしれませんので、直ちに質問席に移動し、一問一答形式で行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。
(降 壇)
近年の国内農業を取り巻く環境は厳しく、農業従事者の高齢化と後継者不足を背景とした耕作放棄地の増加や農業所得の減少が進む中で、食料自給率の向上が求められております。また、世界的に経済連携が拡大を続ける中、貿易自由化促進の波により、日本企業は国内市場の開放とグローバル市場での競争力が求められております。さらには政府が農業を成長産業として位置づけ、支援策の拡充を進めるなど、農業市場、農産物流等は多様化し、大きな変化の中にあります。
本市における農業の現状と課題についてお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
本市の農業は、恵まれた自然環境と伝統技術に支えられ、稲作をはじめ露地野菜、施設野菜、花卉園芸、特産の植木、苗木、ギンナンなど非常に多品目にわたって栽培されておりまして、本市の経済活動や地域の活性化にとって重要な基幹産業の一つでもございます。
課題といたしましては、本市は都市近郊に位置していますことから近年は都市化の進展に伴う農地化や農地の減少、農業従事者の高齢化、後継者の不足、耕作放棄地の発生等が進むなど農業を取り巻く環境は厳しさを増していくことが考えられます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
農業の実態の把握には、農林水産省が5年ごとに全国規模で行う農林業センサス調査がありますが、この調査は農林業の経営体や耕地、作物などを調査し、農業の活性化や振興施設に欠かせない重要な調査であります。
これら調査を踏まえて農家人口の推移について、愛知県の推移と併せてお願いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
本市における農家人口の推移といたしまして、農林水産省が5年ごとに実施する統計調査、いわゆる農林業センサスによりますと、平成17年は6,908人、平成22年は8,428人、直近の平成27年は5,776人、この10年間で16.4%の減少となっております。
一方、愛知県全体では、平成17年は23万9,997人、直近の平成27年は14万1,734人、10年間で40.9%の減少となっております。この農家人口の減少傾向は今後さらに進むものではないかということが見込まれます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
この愛知県と比べて24ポイント差は、数字だけ見れば稲沢市にとってはすごくよいことだと感じますが、少し違和感があります。農家人口は、全体に比べてそこまで減っていないことが分かりました。
では、専業農家及び兼業農家の数の推移について、愛知県の推移と併せてお願いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
専業農家及び兼業農家の数の推移といたしましては、平成17年は専業農家が564戸、兼業農家数が1,680戸、直近の平成27年は専業農家数が436戸、兼業農家数が1,011戸、この10年間で専業農家数は22.7%、兼業農家数は39.8%の減少となっております。
一方、愛知県全体では平成17年は専業農家数が1万1,375戸、兼業農家数が4万263戸、直近の平成27年は専業農家数が1万1,105戸、兼業農家数が2万3,963戸、この10年間で専業農家数は2.4%、兼業農家数は40.5%の減少となっております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
兼業農家についてはあまり愛知県と大差はありませんが、専業農家数が愛知県に対して20ポイント以上のマイナスが気になります。では、農地の地目別経営耕地別面積の推移についてお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
農地の地目別経営耕地面積の推移といたしましては、平成17年は総面積2,051ヘクタールのうち、田が1,133ヘクタールで55.2%、畑が918ヘクタールで44.8%、直近の平成27年は総面積1,625ヘクタールのうち、田が949ヘクタールで58.4%、畑が676ヘクタールで41.6%でございます。全体では10年間で20.8%の減少となっております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
経営耕地面積を市町村別に見ると、減少した市町村は1位が豊橋市、2位が稲沢市、3位が豊田市になっております。稲沢市は、愛知県で2番目になります。
これは豊橋、豊田、稲沢より経営耕地面積が倍以上の都市と一緒なのは、ちょっとひどい状態だと感じております。農業従事者の高齢化や後継者不足による担い手が減少し、今後さらなる農地の経営耕地面積の減少が懸念されます。
国では農業の効率化と高い生産性を図り、国内の農産物の産出額や生産率を上げるために農地の集積、集約化をすることを推進しております。
そこで、本市における農地の集積、集約化の取組についてお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
本市では農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を借りて経営規模を拡大したい農業者と高齢化や仕事等の事情などで耕作できない農地所有者との間で行う農地貸借等の利用権設定や農地中間管理機構が農地所有者から農地を借り受け、まとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して担い手に貸付けを行う農地中間管理事業を活用して担い手への農地の集積、集約化を推進し、農地の有効利用、農業経営の効率化に努めているところであります。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
今回のデータは2015年までですが、最新の農林業センサス2020年は、概要しか出ておりませんが、農家数もおおむね2015年からまた2割減っております。
専業農家、兼業農家は、販売農家、自給的農家と条件と名前が変わっていましたので、何とも言えませんが、地目別経営耕地別面積は、2020年愛知県は10%減少しております。
しかし、1経営当たりの平均経営耕地面積は2015年13%、2020年21.4%と伸びております。これは言うまでもなく、大規模経営は効率がよく、収益化が図られていると感じております。稲沢市はまだデータは出せないとのことでしたが、答弁内容のデータを聞く限りでは愛知県の他市に比べて遅れを取っていると感じております。自治体ごとに特性が違い、一概には言えま
せんが、自治体ごとのデータを見る限り差が激しいように感じます。先ほど答弁にあったように、農業の集積、集約化は市がやることではないかもしれませんが、行政が力を入れることにより流れが変わると感じております。市の将来に深く関わっていくと思っております。強く強く要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。
農産品の品目別生産額の推移についてお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
農産品の品目別生産額ということでございます。
推移を申し上げます。
平成17年の農業産出額は全体で100億2,000万円、内訳といたしまして、米が17億6,000万円、野菜が26億3,000万円、花卉、花でございますが、25億円。植木、苗木が28億7,000万円、畜産が1億円、ギンナンを含みますその他が1億6,000万円でございます。
直近の平成27年の農業産出額は84億円。内訳といたしまして、米が10億9,000万円、野菜が21億6,000万円、花卉が25億3,000万円、植木、苗木が21億7,000万円、畜産が3,000万円、その他が4億2,000万円。この10年間で16.2%の減少となっております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
愛知県全体の農業産出額では、ここまでの答弁を踏まえると下がっていると感じますが、この10年で横ばい、やや増えている状況にあります。農業人口は減っているのですが、産出額はあまり減っていないんです。少し稲沢市の農業に危機感を感じております。
では、販売金額別農家の推移について教えてください。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
販売金額別農家数の推移を申し上げます。
平成17年の販売農家総数は2,488戸、内訳といたしまして、50万円未満が1,024戸、50万円以上100万円未満が378戸、100万円以上200万円未満が343戸、200万円以上が743戸でございます。
直近の平成27年の販売農家総数は1,513戸、内訳といたしまして、50万円未満が714戸、50万円以上100万円未満が164戸、100万円以上200万円未満が177戸、200万円以上が458戸。
販売農家総数が、この10年間で39.2%の減少となっております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
これは愛知県全体と同じような結果ではあります。稲沢市ですと、あまりないですが3,000万円以上の販売金額の経営数はこの10年でかなりの割合で増えております。日本の農家人口は減少していきます。本市においては、農家人口は減少に伴い、米、野菜、花卉、苗木などの生産額や販売農家数も減少し続けております。
このようなことから、その対策として地場産業の育成が必要であると考えております。そこ
で、本市における地場産業の育成の取組についてお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
先ほども御答弁申し上げました本市の農業は、稲作をはじめキャベツ、白菜、ブロッコリーなどの露地野菜、トマト、ミツバなどの施設野菜、菊、シクラメン、鉢花などの花卉園芸、そして特産の植木、苗木、ギンナンなどの多品目にわたって栽培されております。
こうした地場産業の育成には、市場の開拓、地産地消の推進、農産物の高付加価値化など、特色ある取組が重要であると考えております。
また、農作物を生産、加工、流通、販売等の分野まで多角経営を行う6次産業化を推し進めるなど、新たな農業経営の展開が必要でございます。現在、6次産業化推進に向けた人材発掘・育成といたしまして、定期的に6次産業化研修会を開催し、新たな意欲のある農業者の掘り起こしや、企業との連携に努めているところでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
私自身もデータでしか結果を見ていませんが、稲沢市の農業も深刻なフェーズに差しかかろうとしていると感じております。ぜひお願いいたします。
私自身、現在、立会いで地区を回っておりますが、耕作放棄地を非常に多く目にします。また、耕作放棄地の周りの側溝が土で埋まってしまい、水が流れない事例が多々出てきております。
そこで、稲沢市における耕作放棄地の面積について、過去5年間の推移はどのような状況でしょうか。また、愛知県内全域の耕作放棄地の面積も併せてお願いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
耕作放棄地につきましては、農業委員会から地域ごとに委嘱された農地利用最適化推進委員が農地利用状況調査を実施し、現状把握に努めているところでございます。
本市における耕作放棄地の面積は、令和2年度、昨年度でございますが、88.7ヘクタールとなっております。過去5年間の推移を申し上げますと、平成28年度は20.7ヘクタール、平成29年度は24.6ヘクタール、平成30年度は24.1ヘクタール、令和元年度は85.5ヘクタールとなっております。
令和元年度に大幅な増加をした理由につきましては、これまでは雑草が繁茂している耕作放棄地を調査対象としており、植木畑が放棄され、森林化した農地は、農地中間管理機構に借り受けていただくことが難しいことから、調査対象から除外しておりました。しかしながら、このような農地も市民の方々から苦情が多く寄せられることから、現状把握する必要があると判断し、令和元年度より調査を実施したことによるものでございます。
調査方法を変更いたしましたため、一概には比較できないものの、耕作放棄地の面積は増加傾向にございます。
また、愛知県の状況でございます。推移を申し上げますと、平成28年度は2,436ヘクタール、平成29年度は2,270ヘクタール、平成30年度は2,475ヘクタール、令和元年は2,629ヘクタールとなっておりまして、増減を繰り返しておる状況でございます。なお、令和2年度の愛知県全体の面積については、現在集計中とのことで公表されておりません。以上です。
◆1番(杉山太希君)
利用状況調査を行い、耕作放棄地を発見したら、どのように対策をされていますか。また、同じく過去5年間の対応した面積をお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
新規に発生しました耕作放棄地のうち、農地中間管理機構に借り受けていただけそうな農地については、今後の利用方法を把握するため所有者に利用意向調査を実施しております。
その中で自作ができないと回答された農地については、農地中間管理機構へ借受けの有無を照会しております。
意向調査の面接の推移でございますが、平成28年度は4.1ヘクタール、平成29年度は2.8ヘクタール、平成30年度は2.0ヘクタール、令和元年度は3.8ヘクタール、令和2年度は5.5ヘクタールとなっております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
なぜ、農地利用最適化推進委員と利用意向調査で進め方は違うのは分かりますが、ここまで差が出てきていることに疑問を感じております。この利用意向調査は、耕作放棄地の管理者に対して、農地中間管理機構に貸し出しますか、自分で保全管理を行わなければ、課税を1.8倍に強化するといった文を送付します。これに伴い、農地中間管理機構に貸し出さず保全管理すら行わない農地については、現評価の1.8倍に課税が強化されてしまいます。
しかし、ほぼ全ての方が農地中間管理機構に貸し出すという意向を示されるため、実際に課税が強化されることはない状況にあると思います。何か解決策がないかと考えましたが、農業の素人の私には何も浮かびませんでした。解決策の案を要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。
○議長(木村喜信君)
暫時休憩いたします。
午前9時54分 休憩
午前10時02分 再開
○議長(木村喜信君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
杉山太希君。
◆1番(杉山太希君)
今後も農業従事者の減少と高齢化の進行が見込まれますが、本市の農業を維持・継続させるための農業の後継者対策の見解についてお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
我が国の農業は、国の統計によりますと、農業従事者の平均年齢が67歳と非常に高く、高齢化が進行している状況でございます。この状況は、本市においても同様でございまして、今後持続可能な力強い農業を実現していくためには、将来の担い手の確保や新規就農者の育成をするとともに、担い手に農地を集積していくことで営農地の効率的な利用を促進していくことが重要であると考えております。
◆1番(杉山太希君)
今後も農業従事者の減少と高齢化の進行が見込まれる中で、次世代を担う農業者の育成の取組についてもお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
次世代を担う農業者を育成するための対策といたしまして、国の農業次世代人材投資事業がございます。
この事業は、平成24年度から新規就農・経営継承総合支援事業として国が実施し、平成29年度に農業次世代人材投資事業に名称変更されております。
この制度の概要といたしましては、年齢が50歳未満で、農業を開始して間もない新規就農者の方に対しまして就農直後の生活安定、経営確立を支援する資金として、1年につき資金を最大で年間150万円、最長で5年間交付するものでございます。
具体的な支援内容につきましては、新規就農に関係する機関・団体等が連携して、資金面だけでなく農地のあっせん、継続して営農を行うために農業経営や技術習得に対しての指導、それから地域農業に関する情報公開などを行っております。
本市では、平成25年度からこれまでに7名の方にこの事業を活用していただき、総額2,370万円を交付し、現在4名の方が交付対象者となっております。今後も、本事業を有効活用しながら、就農定着のための支援を継続し、新たな就農者の掘り起こしにも努めてまいりたいと考えております。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
農の雇用事業の支援を受けて、新規就農1,591人のうち、3年目までに離農した人数は564人と全体の35.4%にも上っております。就農後のサポートにも力を入れていただくようよろしくお願いいたします。
今後も農業従事者の減少と高齢化の進行が見込まれる中で、新規就農者対策の取組についてお伺いいたします。
◎経済環境部長(岩間福幸君)
現在、全国的に農業従事者の高齢化や後継者不足が進行しております。農業を将来にわたって発展させていくためには、新規就農者の育成・確保が必要不可欠でございます。
そのため、本市では一宮市と愛知西農業協同組合と協働で、農業者の高齢化や後継者不足に対応するため、はつらつ農業塾を開講し、将来の農業者の育成に努めているところでございます。
その結果、これまでに本市では7名の方が新規就農者として営農し、新規就農者の定着につながっております。なお、この現状は決して十分ではございませんが、今後も関係機関との連携を強化しながら、新規就農者確保に向けた取組を積極的に推進してまいりたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
外国人労働者に目を向けてみてはどうでしょうか。工場、コンビニ等、最近ではたくさんの外国人労働者を見かけますが、稲沢市では私の肌感覚ではありますが、農業の現場で外国人を見たことがありません。
農業分野の外国人研修生は17年には13年の1.9倍の6,606人となっており、また技能実習への意向を申請した者は、13年の5.4倍の2,758人に急増しております。農繁期に不正に超過研修や休日研修が行われる例があること、研修の実施体制や研修、技能実習生の管理が不十分な受入れ機関があること等の課題もありますが、よろしくお願いいたします。
最近では、ドローンで農薬を散布されている農業従事者も稲沢市では見かけるようになりました。外国人技能実習生の採用、ITの導入による農業の効率化、さらに通勤農業という新しい就農の形も見えてきております。農業が魅力的な職業として再認識されることが農業人口の増加につながるのではないでしょうか。今後は、稲沢市も都市化する地区は、規制緩和でどんどん都市化し、農業の地区は農業で効率化、集約化、スマート化を要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。
非常食の備蓄の現状についてお伺いいたします。
災害備蓄品はどの地域でもある程度同じなのかなと思っておりましたが、それぞれの県や市で全く異なることが分かりました。さらに、県、市、区、町、村、自治会などでそれぞれ違うものを備蓄していたりもします。
そこで質問させていただきます。
稲沢市が備蓄をしている非常食の量は、何日分の想定で何人分備蓄されているでしょうか。
◎総務部長(平野裕人君)
南海トラフ地震が発生した場合における愛知県の被害試算では、本市では発災後、1日で7,500人の方が避難すると想定されております。この1.2倍に当たる9,000人分の食料として、
1日3食、3日分である8万1,000食を備蓄いたしております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
備蓄している食料についてですが、どのような種類の非常食を備蓄されているでしょうか。
◎総務部長(平野裕人君)
水を加えることで食べることができる白飯、ワカメ御飯、キノコ御飯のアルファ化米や玄米でできたスナックなどを備蓄いたしております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
その非常食についてですが、一般の方だけではなく、アレルギーをお持ちの方や高齢者の方に対しての考慮はなされていますか。
◎総務部長(平野裕人君)
先ほど申し上げた非常食につきましては、令和元年度までは27品目、それから令和2年度からはアーモンドが増えまして28品目になりましたが、アレルギー物質を使用していないものを備蓄いたしております。
また、高齢者の方が食べやすく、状態としては柔らかく消化がよいおかゆについても備蓄をいたしております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
それらの非常食は、どこに備蓄されていますか。
◎総務部長(平野裕人君)
稲沢中学校をはじめとした小・中学校など指定避難所、市内40か所それぞれの防災倉庫に備蓄いたしております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。
ほかの自治体等では総合備蓄拠点のような1か所に備蓄していて、避難所には備蓄していないという地域もあるようなので安心いたしました。
神戸市の例ではありますが、備蓄を4種類に分類しているそうです。市民備蓄、市民が自分たちで持っている非常食、流通備蓄、コープやダイエーなど神戸市が協定している業者等から提供される物資、現物備蓄、各避難所等に備蓄されている神戸市が用意している備蓄品、救援物資、国や他の自治体等から調達される物資です。近年では、稲沢市に幸いに大きな震災が起きていない分、市民の防災意識を上げるのは相当難しいと思いますが、神戸市では震災からの教訓を生かし、非常食の備蓄に力を入れているので神戸モデル等も参考にしていただけると幸いです。
次の質問に移らせていただきます。
私自身、区長等に区での非常食事情について聞いてきましたが、非常食を備蓄している区は
少数だと分かりました。区も防災倉庫を持っていたりするので、少しでも区、個人に補助金を稲沢市から出して防災意識を高めてもらおうと名案を思いついたのですが、平等性、税金を使ってどこまで備蓄するかの観点から相当難しいことが分かりました。
また、先ほど答弁したように、農業は相当苦しい状況にあり、食の有効活用の観点から稲沢市で生産した米を加工した非常食を製造し、流通させることも方法ではないかと考えましたが、既存システムがあることから現実的には大変困難であると思われます。
そこで市にお伺いします。この先、非常食の備蓄量を増やしていく想定はあるのか教えてください。
◎総務部長(平野裕人君)
現在、備蓄量を増やすことは考えておりません。しかし、これまで5年保存の非常食の備蓄をいたしておりましたが、経済性・効率性の観点から7年保存の非常食に移行することなどを検討していきたいと考えております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
現在の備蓄している食料が賞味期限切れになった際にはどのようにしておりますか。
◎総務部長(平野裕人君)
備蓄しております非常食につきましては、防災意識の向上を図るため、賞味期限が近づく前に小・中学校に通う児童・生徒に配付するなどして非常食の体験をしていただいたりしております。以上です。
◆1番(杉山太希君)
私も最近非常食を様々食べてみましたが、おいしいもの、まずいもの、期限の長短、多種多様な非常食があることに気がつきました。小さい頃から非常食に触れることはすごくよい体験だと感じております。
最後になりますが、現在はメディア等の影響により防災意識の向上が図られてはおりますが、現状は非常食等を備蓄している家庭は50%〜60%となっております。10年前のアンケートを見ると、80%となっているものもありました。これは、東日本大震災で皆さんの防災意識が高くなっていたのかなと感じております。地域に関しても、関東地方は60%、中国地方では24%という結果になっております。地域の防災意識の差も歴然です。これからの防災に関して地域性を確かめるためにも、一度稲沢市でもアンケートを取ってみたらどうでしょうか。
そして、非常食を備蓄されている方で、非常食の賞味期限切れを経験した方が75%という結果が出ています。それを解消する一つの手段として、日頃から食べ慣れた食品を備蓄し、ふだんの食事で消費をした分を補充するという日常的なローリングストックがいざというときの対策になると考えております。自宅でローリングストックをすることにより、防災力の向上を図れること、防災意識が高まることの重要性を市民の方にPRすることをさらに力を入れていた
だくこと、併せてアンケート調査の実施を要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
令和2年12月定例会(12月14日)映像はこちら
主な内容
1.コミュニティバス、お出かけタクシーの現状について
(1)今後の展開について
2.コロナ禍の財政状況について
(1)今後の展望について
(2)予算編成について
(3)学校教育の影響について
3.投票区、投票所再編について
(1)投票所を減らした影響について
(2)市民の声について
以下は議事録です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。日本の教員は授業以外の業務が多く、世界で一番忙しいと言われております。新型コロナウイルスの影響で負担はさらに増してきておると思っております。
一斉休校の期間が終わってから半年近くたっても、学習の遅れを取り戻したり、過密な授業日程、日本教育組合が全国の小・中学校や高校などを対象に行った調査によると、冬休みを短縮する学校は3割以上に上ると聞きます。毎朝7時に出勤し、登校してきた子供の健康状態のチェッ
ク、密集を防ぐため、クラス全員分の給食を取り分けている教員もいるとお聞きします。放課後には全ての机や椅子も消毒して回る。
国は、教員3,100人を追加配置し、授業を手伝う学習指導員を約6万人増やす予算措置を講じました。しかし、退職教員をはじめとする要員の確保が容易ではなく、追加の教員は6割、学習指導員は8割しか活用されていません。雑務を補う学校支援員は約2万人が追加配置されましたが、勤務時間が限られ、放課後には働けないケースが多いそうです。
そして、これから始まるGIGAスクール、やはりこのGIGAスクール構想には、総額20億円近くの税金が投入されております。宝の持ち腐れにしては絶対いけないと思っております。タブレットだけが配付されて、はいよろしくでは先生たちも使えないと感じておりますので、どうか厳しい財政ではありますがICT支援員の増員を要望して、次の質問に移らせていただきます。
投票区、投票所再編についてお聞きします。
今回、志智 央議員と質問が重なってしまいましたので、少し違う観点から質問をしていきたいと思います。
今回の稲沢市長選挙は、コロナ禍、そして投票区、投票所再編後の初の選挙でした。投票所が廃止された地区とそれ以外の地区で、それぞれ再編前と再編後で投票率にどのような影響がありましたか、お伺いいたします。
◎総務部長(清水澄君)
選挙の投票率につきましては様々な要因が複合的・総合的に関連するため、1つの要因との関連だけでは一概には申し上げられませんが、今回の市長選挙と似た構図でございました平成26年のそれと比較いたしますと、全体の投票率としては、平成26年度は37.33%、今回は32.99%でございましたので、4.34%の低下となっております。
投票所が廃止された地区と、それ以外の地区での投票率の増減につきましては、ほとんどの地区で今回投票率は低下しております。また、それぞれの投票区の投票率の増減の比較についても、先ほど申し上げましたように様々な要因が関連して単純な比較が難しいところではございますが、廃止した7投票区を含む9投票区でマイナスの5.55%、それ以外の22投票区でマイナスの3.12%でございますので、その差は2.43%でございます。以上でございます。
◆1番(杉山太希君)
今の説明で投票率の増減については一概に言えないことは理解しました。私が思っていたより影響は出ていないのかなあと感じております。
新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言が出された4月7日以降、全国の選挙で過去最低投票率が相次いでおります。市区長選挙では7割強が過去最低を記録しております。
1月19日から4月5日に実施された18の選挙では、前回より投票率を下げた自治体が多かった
ものの、過去最低は7選挙にとどまっております。一方、7都道府県への緊急事態宣言直後、4月12日の選挙では8市中7市が過去最低の投票率となりました。同19日も含めると、15市区長選挙のうち11市、73%で過去最低となっております。7市区長選挙のうち過去最低とならなかった3つの自治体では、前回よりも投票率が上昇しております。しっかりとした対抗馬がいる場合、有権者は今回は投票したほうがいいとなる一方、そうでない場合にはリスクを冒してまで投票に行く必要はないと考える人が多かったのかと思います。これが投票率の二極化につながっているのではないでしょうか。
今回のコロナで、ほかの自治体、他県の政治家の行動や発言を見て、頼りになる人物なのかそうでないのかという差が明らかになり、市民が政治家を選ぶことの意味が浮き彫りになったと思います。
今回の稲沢市長選挙でも過去最低の投票率ではありますが、得票率で言えば、今回の市長選挙と似た構図であった平成26年と比べると、加藤市長のほうが上回っております。感染リスク、そして投票所の再編があったとしても、投票行動にはそれを上回る価値があると考えた人が多かったはずです。今ほど政治によって生活が変わるということを実感できるという機会はないからだと思っております。今後の各選挙の結果なども注視して、分析、検証を継続していただきますようお願いいたします。
それでは、今回の投票区、投票所の再編について、経費の面から質問いたします。
今回の再編で投票区が38から31に7か所減りました。その結果、選挙に関わる経費についてはどのような影響がありましたか。
◎総務部長(清水澄君)
投票所等の再編により、選挙経費に大きく影響のあったものといたしましては、投票管理者が7人、投票立会人が14人、事務従事者が34人削減され、それに伴いまして報酬、時間外勤務手当等の人件費が109万1,050円の減少となりました。また、ポスター掲示場設置等委託料とその謝礼で56万5,400円、そのほかに民間投票所借り上げ料や投票所受付等業務委託料などの物件費が減少いたしましたが、逆にバリアフリー化、土足対応などとして増加している部分もございまして、全体としては差引きで約17万円の減となったものでございます。
なお、今回の再編の大きな目的であります新型コロナウイルス感染症対策に係る費用につきましては、全部で205万2,755円が別途生じたものでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。コロナ対策の費用が思った以上かかっていることに驚いております。
今後バリアフリー化が進み、そしてコロナが終息に向かえば、それらに係る初期費用や継続費用がなくなると思います。その経費を使ってさらなる投票環境の向上、投票機械の提供の拡充につながる施策を取ることはできないでしょうか。例えば期日前投票の新設などです。
そこでお聞きしますが、現在、期日前投票のリーフウォーク稲沢での経費はどのぐらいかかっておるでしょうか。
◎総務部長(清水澄君)
リーフウォーク稲沢で期日前投票を導入した平成31年2月の愛知県知事選挙のときでいいますと、ネットワーク施設やパソコン購入などの初期費用が155万6,820円、通信などの継続費用が年間36万2,880円でございまして、そのほかに期日前投票所の開設期間中は、運営費用が1日当たり18万1,472円かかることになります。今回の再編後の課題でございます期日前投票所の拡充につきましては、今後、他市事例等の調査・研究を進めるとともに、大型商業施設等への働きかけなど前向きに検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上です。
◆1番(杉山太希君)
ありがとうございます。今後、バリアフリー化の進展、コロナの終息によって削減された経費については、期日前投票の拡充や選挙の啓発、主権者教育などに充ててもらうよう要望して一般質問を終わらせていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和2年9月定例会(9月15日)映像はこちら
主な内容
1.人事について
(1)就職、離職、休職について
(2)中途採用について
(3)若手の指導について
(4)人事評価について
(5)残業について
(6)女性雇用について
以下は議会だよりより抜粋したもの
Q,今後の稲沢市をよりよくするためには、人事制度が重要な役割であると考えている。多種多様な人材を採用するという観点から職員の採用試験に(※)SPIなどを導入する考えはないか。
A,現在、本市では、採用試験として教養試験と適性検査を行っている。
SPIは、適性検査の一つとして、学力や知識だけを問うものではなく、色々な側面から総合的に判断するテストであるが、現時点では、市職員として学力なども重要な要素と考えており、SPIの具体的な導入予定はない。
導入の可否については、今後、先行他市の事例を研究する中で考えていく。
Q,市の組織を活性化するため、民間企業経験者を積極的に採用してはどうか。
また、中途採用の現状や今後の展望は。
A,職員採用において、特別に民間企業経験者の枠を設けることはしていないが、受験資格の対象年齢に幅を持たせて募集を行っており、民間企業経験者も受験できるようになっている。
実際に毎年度、新規採用職員のうち、数名が民間企業からの転職者であり、優秀な人材も多く採用できているので、引き続き同様な取り組みを行っていきたい。
※SPI・・・
総合適性検査の略称で、多くの企業で採用選考の際に用いられている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和元年 12月定例会(12月10日)映像はこちら
主な内容
1.市街化調整区域について
(1)現在の状況について
(2)稲沢市の市街化区域が少ない原因について
(3)市内11駅の周辺について
(4)稲沢市都市計画法に基づく開発行為の許可基準改正による今後の方向性について
(5)リニア開通に向けた今後の考え方について
2.稲沢市のPR力について
(1)PRで最も力を入れていることについて
(2)稲沢市シティープロモーションサイトの閲覧数について
(3)市外へのプロモーションについて
(4)発信力を強化するために何を考えるか
以下は議会だよりより抜粋したもの
Q、人口減少という課題に対し、定住促進のPRを行う必要があると考えるが、最も力を入れている取り組みは。
A、課題の一つに「名古屋圏における本市の認知度不足」があるため、本市の存在を知っていただく取り組みを最重要視している。その中でも、シティプロモーション特設サイトの運用に注力しており、定住促進に向けた情報発信のプラットフォームとして活用したい。
Q、情報の発信力において、広告に投じる予算は重要であるが、これまでの事業費は。
A、シティプロモーション事業に関する当初予算額は、昨年度は600万円、今年度は200万円である。昨年度は事業初年度のため『稲沢市シティプロモーション戦略』の策定、特設WEBサイトの開設を実施している。今年度は、特設サイトのコンテンツの拡充及び特設サイトへのアクセス誘導のためのWEB広告費が主な事業内容である。
Q、広告展開は費用を投じても実施すべきと考えるが市長の考えは。
A、都市計画や住宅政策と足並みを合わせ、PRの費用対効果が最大限に発揮されるタイミングで実施すべきと考えている。現在のところは、認知度向上に向け、ホームページのコンテンツ拡充を中心にPRに努めたい。